40代で転職や昇進を目指す際、大きな武器となるのが資格です。各業界で求められるスキルや専門性を証明でき、それによって自分の市場価値を高めてくれるため有利です。特に、「食いっぱぐれない資格・食える資格」など、それさえあれば就職先に困ることがない資格を取得できれば、思い切った転職にも踏み切ることができます。
同時に、資格取得を通じて培った学びや努力のプロセスで自分に自信がつき、成長へのモチベーションアップにもつながります。企業に向上心の高さを示すこともできるので、そういう意味では「意味のない資格」はありません。
ここでは、「40代でも資格取得を目指したのほうが良いのか」、「どの資格が転職で有利になるのか」など資格取得で迷っている人に向け、資格選びのポイントや転職に有利になるおすすめの資格一覧、資格取得を成功させるコツ、キャリアで活かすヒントなど、資格取得に関するあらゆる疑問に答えていきます。
目次
40代の転職では、なぜ資格取得が有利になるのか?
40代の転職に有利な資格とは?資格選びの3つのポイント
40代の転職が有利になる資格一覧
40代でも大丈夫!資格取得を成功させる3つのコツ
40代の転職 資格取得をキャリアで活かすヒント
40代から一生できる仕事の特徴
40代から一生できる仕事を見つけるコツ
40代の転職に有利な資格でよくある質問(FAQ)
40代の転職を目指すなら転職エージェントの活用が効率的
40代の転職では、なぜ資格取得が有利になるのか?
40代の転職では、「資格」「資格取得」は非常に大きな意味を持ちます。自分自身の能力や学習意欲の裏付けとなり、書類選考通過の確率を上げたり、キャリアの選択肢を広げたりするからです。なぜ、資格取得が40代の転職で有利になるのか、具体的に見ていきましょう。
自身の能力の裏付けとなり、他者と差別化が図れる
40代などミドル層の求職者に対しては、企業は単なる知識だけでなく、その知識を現場で活かしてきた経験値を求めます。そして資格は、これまでのキャリアで培ったスキルや専門性を客観的に示す証拠となり、採用担当者へ説得力のあるアピール材料となります。
たとえば、簿記2級・FP2級・中小企業診断士を所持していると、経理・金融・経営分野での実力を証明でき、即戦力人材としての信頼性を高め転職に成功しやすくなります。TOEICやTOEFLは、英語でのコミュニケーション能力を補強してくれる信頼できる資格です。
これらの資格と今まで培ってきた実務経験を組み合わせてアピールすることで、経験値だけ、資格だけにならない「40代の強み」として、ライバルと差をつけられる武器となります。
未経験分野での転職では、書類選考通過の可能性を高められる
近年、エイペックスでも40代の転職希望者が増えています。40代は、「ある程度経験を積んできたが成長が止まってしまった/役職が上がらなくなった」という人が増える時期で、思い切って業界や職種を変える人も多く出る世代です。
しかし、40代で未経験というのは採用が非常に難しく、基礎力や適性を履歴書上で証明しておかないと、採用面接まで到達するのは困難です(一部の慢性的な人手不足の業界・職種は除く)。
たとえば、ITパスポートや基本情報技術者の資格は、ITの基礎知識を持っていることが証明でき、これからIT業界を目指す場合に取得しておきたい資格です。医療事務や登録販売者は未経験からでも挑戦しやすく、医療業界への転職やライフステージに合わせた働き方を重視するときに向いています。宅地建物取引士や社会保険労務士など、独占業務を伴う国家資格は「食いっぱぐれない資格」として人気で、実務経験がない場合でも採用の可能性が高まります。
このように、40代での資格取得はキャリアの再設計や人生のリスタートをサポートしてくれる存在になり得ます。資格取得を通じた努力や向上心も採用担当者にアピールでき、書類選考通過の可能性を高めてくれるでしょう。
資格取得のための勉強で、業界・転職先への理解力を高められる
資格取得のための学習は、転職先の業界や企業への理解力を深めるための大切な手段となります。取得に向けた勉強が、業界・転職先に求められる体系的な知識を学ぶためのステップとなり、入社後に行う業務でも役立ちます。
また、資格取得のため勉強をしていたということは、面接官に対して
向学心がある
最新の情報に接している
論理的思考力を持っている
ことをアピールする材料にもなります。学習は単なる資格取得の手段ではなく、自身のキャリア形成を豊かにする重要なプロセスです。
40代の転職に有利な資格とは?資格選びの3つのポイント
では、40代の転職に有利な資格とは、どのようなものなのでしょうか。
ここでは、「どのような資格を取れば良いか迷っている」という人のために、以下の3つの資格選びのポイントをご紹介します。
今までの経験に基づいた資格を選ぶ
「稼げる資格」を選ぶ
「資格の取りやすさ」を考える
それぞれ見ていきましょう。
① 今までの経験に基づいた資格を選ぶ
40代で取得すべき資格に迷った場合は、まず「今まで自分が行ってきた業務に関連する資格」の取得を目指しましょう。自身の業務経験や役割から得たスキルを可視化し、それを次のステージでどのように活かせるかを考えたうえで、資格取得に向けて準備します。
たとえば、これまで管理業務や組織運営に携わってきたのであれば、マネジメントや労務分野の国家資格に目を向けることで、実績と知識の両方をアピールしやすくなります。
新しい分野への挑戦を目指す場合でも、これまでのキャリアと親和性の高い分野での基礎的な資格を選ぶことが着実な一歩となります。技術職から営業職、あるいは事務系職種へのキャリアチェンジであれば、まずは汎用性の高い資格や、現場での即戦力となる基礎知識を身につけられる資格を選ぶのが効果的です。
外資系や日系グローバル企業への転職であれば、英語の資格は非常に汎用性が高いため取得を目指すべきです。
このように、自身の経験を補強・拡張できる組み合わせを意識することで、転職市場や今後のキャリアでのアピール材料となります。
② 「稼げる資格」を選ぶ
資格選びのポイントの2つ目として、「稼げる資格を選ぶ」という選択があります。
稼げる資格とは、
将来性がある
専門性がある
需要がある
というものです。
たとえばIT系の資格は需要があり、特にデータ活用やセキュリティ関連、クラウド系の資格は専門性の高い人材としての証明になります。弁護士や不動産鑑定士、電気工事士などの独占業務を持つ資格であれば、専門性が極めて高いため確実に「稼げる」「食べていける」資格だといえるでしょう。
なお、IT化や自動化が進行しても介護や医療の仕事はニーズがあり続けるため、これらの資格も非常に強いものだといえます。
③ 「資格の取りやすさ」を考える
「この資格があれば高収入が見込め、転職先にも困らない」という資格であっても、取得までに膨大な時間がかかるものであれば、現実的には目指すことは難しいといえます。
たとえば文系の最高峰の資格といわれる弁護士資格は、取得までに3,000~10,000時間かかるといわれ、毎日3時間勉強していたとしても3年~10年ほどかかる計算です。社会人組が目指す場合は、相当以上の覚悟がなければ取得できない資格です。
このように、資格取得を目指す場合は取得までのおおよその時間を割り出し、かつ試験日から逆算して学習計画を考える必要があります。特に、「働きながら資格取得を目指す」という場合は、しっかり計算して計画的に学習を進めることが大切です。
難関試験や国家試験を考える人は、
試験の難易度が自分に適切か
自分がその分野に興味を持てているか
勉強できる環境が整っているか(あるいは整えられるか)
目指す転職活動時期に試験日・合格発表日が間に合うか
を確認することも重要です。
40代の転職が有利になる資格一覧

ここからは、40代の転職に有利になる資格をジャンル別にご紹介します。自分と関わりの深い業界や、これから進みたい業界の資格をチェックして、資格選びの参考にしてみてください。
ビジネス・マネジメント・金融
日商簿記2級以上:【学歴・実務経験不要】70年以上の歴史を持つ資格であり、企業の経理や財務など管理部門での転職・昇進に有利。1級・2級・3級・ほか下位資格があり、経理・財務部門でのアピールとなるのは2級から。1級の取得で、大企業の経理部門でもかなり有利になる。
ファイナンシャルプランナー(FP2級・1級):【2級は実務経験不要、1級は実務経験必要】資産運用やライフプラン設計だけでなく、金融機関や保険会社での顧客提案力を証明する資格。個人顧客向けのコンサルや独立開業も可能。2級の場合、3級の資格があれば実務経験不要だが、1級は「2級取得+1年以上の実務経験」もしくは5年以上の実務経験が受験資格と定められている。
公認会計士(CPA):【学歴・実務経験不要】高度な会計スキルを証明でき、財務や監査関連のキャリア構築を目指す人にとって非常に有用な資格。「監査証明」という独占業務も持っているため、転職先には困らない。
ただ、公認会計士は難関資格のうちのひとつで、取得には2,500時間以上の勉強が必要とされている。日本のCPAだけでなく、米国公認会計士(USCPA)など海外の資格も転職で有利。税理士:【学歴・資格・実務経験のいずれかが必要】税のスペシャリストであり、独立開業することもできる資格。受験の際は、学歴・資格・実務経験のいずれかの条件を満たしていることが必須。
ただ、財務部門において強力なアドバンテージとなる一方、資格取得までに4,000時間程度の学習が必要とされる難関試験。前述の「日商簿記1級」は、税理士の受験資格のうちのひとつ。弁理士:【学歴・実務経験不要】知財関係のエキスパートになれる資格であり、紛争解決にも携われる非常に有用な資格。税理士・会計士と並んで難易度の高い資格とされ、3,000時間ほどの勉強が必要である一方、学歴・実務経験は問われない。
中小企業診断士:【学歴・実務経験不要】企業の経営戦略に対してアドバイスが可能になる資格であり、コンサルタント業務を担える。試験は、一次試験→二次試験筆記→二次試験口述の3段階から成り、前の段階をクリアしていないと受験できない。一次試験は学歴・実務経験不要で受験可能。
証券アナリスト(CMA):【受講必要】投資分析や企業評価の専門知識を持ち、金融業界や事業会社の資産運用部門でのキャリア構築に有利に働く資格。資格取得には証券アナリスト講座の受講が必須だが、より高度な資格を取るためには実務経験などが求められる。
PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル):【実務経験必要】プロジェクト管理スキルを示す国家資格で、世界的に認知されている資格。IT企業への転職に強く、日本国内にとどまらない活躍を目指す人にもおすすめ。受験には、最低でも3年4,500時間のプロジェクトマネジメント経験と教育機関での研修が必要(高卒は、実務経験(5年以上かつ7,500時間以上)+研修)。
知的財産管理技能検定:【学歴・実務経験不問】知的財産関係に関わる国家資格であり、著作権のほか種苗法や特許法なども網羅する資格。製品開発や著作物を取り扱う業界・企業を目指す人におすすめ。1級・2級・3級があり、3級は受験資格がなく、2級以上は下位資格の合格・実務経験・学歴のいずれかが求められる。
行政書士:【学歴・実務経験不問】行政手続きのスペシャリストで、官公庁などに出す書類の作成や手続きを行える資格。書類作成に関する独占業務を持ち、かつ士業でありながら取得までにかかる勉強時間は800時間程度(当該分野未経験から)と短いため、「今から士業の資格を取得したい」と思っている人にもおすすめ。
MBA:【学歴or入学資格審査必要】資格ではなく経営学修士で、企業経営に必要な知識やスキルを体系的に学ぶ大学院レベルの学位。日本の大学院(ビジネススクール)に通うか、海外の大学院に留学して取得する方法がある。戦略・経営コンサルティング、マーケティング、事業開発・経営企画、投資銀行・PEファンド・VC、外資系企業のマネジメント職などへの転職の際に有利に働く。
なお、これ以外にも有用な資格として、「弁護士」があります。ただこれは非常に難易度が高いため、ここでは取り上げていません。
医療・福祉・生活支援
介護職員初任者研修:【学歴・実務経験不問】介護の知識がなくても受講~取得可能な資格であり、介護現場での就業・転職を目指す際のスタートラインともいえる資格。高齢者福祉施設や訪問介護の現場で、即戦力として歓迎される。
栄養士:【学歴必要・実務経験不問】「栄養」に関わる資格であり、保健指導や集団給食、健康経営など幅広い領域で活躍できる。健康志向や高齢化社会の流れに合わせ、食・健康分野の専門家として重宝される。取得には栄養士のための養成機関を出ている必要があり、さらに上位の資格である管理栄養士を目指すこともできる。
医療事務:【学歴・実務経験不問】病院やクリニックでの受付・会計・保険請求業務の基礎を身につけられる資格。育休中に取得する人も多く、短時間勤務や転職にも対応しやすい。
介護福祉士:【学歴もしくは実務経験必要】介護関連の資格の代表的なもののうちのひとつで、国家資格に分類される。養成機関を経て受験資格を得るのが一般的だが、実務経験3年以上があれば養成機関を経なくても受験ができるため、「すでに介護の業界にいるが、介護の学校は出ていない」という人におすすめ。
調剤薬局事務:【学歴・実務経験不要】調剤薬局やドラッグストアでの受付・会計・保険請求に対応できる資格。医療業界への入口となる資格で、柔軟な勤務スタイルも選択可能。学歴や実務経験は不要だが、医療保険調剤報酬事務士講座の受講が必要。
登録販売者:【学歴・実務経験不要】 ドラッグストアや小売等での市販薬の販売に関する専門的業務を担うため、店舗運営に欠かせない資格。未経験からの就業や、家庭と両立できる働き方に適している。かつては実務経験が必要であったが、現在はこれが撤廃されている。
社会保険労務士:【学歴必要】労働法務や社会保険手続き、働き方改革の推進役として、企業の人事・労務部門や社労士事務所で幅広く活躍できる資格。福祉大学で指定科目を履修することで受験資格が得られるが、相談援助実務4年以上でも受験可能。ただしこの場合は、一般養成施設などで1年以上の勉強が必要になるため、どのコースであっても、なんらかのかたちで「養成機関で学ぶ」という工程が必要になる。
看護師:【学歴必要】医療系資格のなかでもっとも知名度が高い資格であり、かつ高いニーズを誇る資格。養成機関の卒業+国家資格試験合格とハードルは高いものの、常に有効求人倍率が2倍を超える職業であるため、社会人組が夜学(あるいは一度退職して)目指すケースもよく見られる。
医療・介護現場への転職を希望する場合は、地域や職種に特化した転職サイトを活用するのも有効。例えば、医療キャリアナビは看護師を中心に、関東・関西エリアの医療・介護職に特化した求人を扱う専門サイトで、現場で専門性を活かしたい人のキャリア形成を支援している。
なお、医師資格など非常に難易度が高い資格や、実務経験がないと取得してもあまり意味のない資格は取り上げていません。
IT・デジタル・技術
IPA主催IT試験(ITパスポート/基本情報技術者/応用技術情報者):【学歴・実務経験不要】いずれもIPA(情報処理推進機構)が主催する国家試験。ITパスポートがIT資格の入門編、基本情報技術者がITエンジニアの登竜門的試験、応用情報者がその次の段階となる。一般レベルの教養として取得するのであればITパスポート試験だが、実務に耐えるレベルを求めるなら基本情報技術者試験以上がおすすめ。
その他、レベルや専門領域に合わせて13種類の資格がある。AWS認定ソリューションアーキテクト -アソシエイト:【実務経験1年以上】AWS (Amazon Web Services) が主催し、クラウド上で分散システムを設計・構築するスキルを証明する資格。「アソシエイト」は中級レベルの認定資格で、実務でAWSを扱う機会がある、もしくは増やしたい人向け。さらに上位に「プロフェッショナル」があり、クラウドシステムの設計・実装経験2年以上の人が対象。
CAD利用技術者試験:【基本的には制限なし】製造業・建設業の設計部門で必須のスキル。ハローワークでも職業訓練のうちの1つに取り上げられており、信頼度と知名度が高い。図面作成や設計業務のデジタル化が加速するなかで、実務力の証明となる。
不動産・建築・電気・管理系
宅地建物取引士:【学歴・実務経験不問】不動産売買や賃貸契約の現場で独占業務を行えるため、不動産業界で非常に強いアドバンテージとなる国家資格。法律で、「宅地建物取引業者は、最低でも1人以上の宅地建物取引士を置かなければならない」と定められている。
土地家屋調査士/測量士:【学歴・実務経験不問】土地や建物の表示登記、境界確定業務で活躍する資格。どちらも国家資格だが、前者は法務省の、後者は国土交通省の管轄する資格であり、仕事内容に微妙な違いがある。市再開発やインフラ整備の進展に伴い、安定したニーズがある。
賃貸不動産経営管理士:【学歴不要・実務経験は求められる】賃貸不動産のスペシャリストとなる資格で、2021年から国家資格となった。不動産管理会社やオーナー支援業務でのキャリア形成が考えられる。なお、受験においては学歴も実務経験も不要だが、登録する際には2年以上の実務経験が必要になる。
不動産鑑定士:【学歴不要・実務経験は求められる】不動産の資産評価やコンサルティング業務に特化した資格。金融機関や公共団体でも、専門職として高い信頼を得ている。受験に制限はないが、登録時には2年以上の実務経験(あるいは実務講習の修了)が求められる。
管理業務主任者・マンション管理士:【学歴・実務経験不要】 両方ともマンション管理に関わる仕事で、国家資格。 前者は管理組合などに対して契約事項を説明する業務などを行い、後者はマンションの維持に深く関わる仕事。両方とも受験に必須となる学歴・実務経験はない。
電気工事士:【2種までは学歴・実務経験不要】建築・設備現場での電気工事や保守管理に従事できる国家資格。インフラ関連の安定した需要が続いており、手に職を付けたい人に最適。1種・2種・3種とあり、それぞれで取り扱うことのできる範囲が異なるが、転職などで役に立つのは2種から。なお2種は学歴・実務経験が不要でだが、1種の場合は登録に実務経験が求められる。
施工管理技士:【受験項目によって異なる】7種類14段階から成る資格の総称。建築・土木・電気工事・造園・建設機械・電気通信工事の7つかつ2段階の難易度に分けられ、すべて国家資格に分類される。受験難易度や受験資格は種類によって異なり、当該分野における工程管理や原価管理、安全管理、品質管理、環境管理の実行性を担保するものであり、その分野で高い評価が得られる。
その他の専門資格
危険物取扱者:【受験項目によって異なる】製造業・物流業・インフラ関連企業での安全管理に不可欠な資格。乙・丙・甲に分けられていて、乙・丙は学歴・実務経験不問で受験可能だが、甲の場合は学歴などが必要になる。特に乙種第4類は幅広い現場で重宝される。
旅程管理主任者:【実務経験必要】旅行業や観光産業でのツアーコンダクターや添乗員として必要な資格。国家資格ではないが、募集型企画旅行を行う企業では旅程管理主任者の配置が法律で義務付けられているため、旅行業界への転職を目指す場合に取得したい資格。インバウンド需要増加のなか活躍の場が広がっているが、基本的には現在旅行業に従事する人がステップアップのために取得する資格。
登録日本語教員:【コースによって異なる】日本語を母国語としない人に対し、日本語を教えるための資格。日本国内のみならず海外でも活躍の場が見込める資格だが、就くためのルートは学歴や実務経験により異なる。英語がまったく話せなくても取得可能。
キャリアコンサルタント:【講習受講が必要】組織内外での人材育成やキャリア支援を行う専門職で、現在は国家資格とされている。一般企業の人事部門のほか、大学等での進路・就職課や、ハローワーク等の公的機関、転職エージェントなどで活躍の場がある。
TOEIC/TOEFL:【学歴・実務経験不要】両方とも総合的な英語力を証明する資格だが、日本国内ではTOEICが圧倒的に認知度が高く、採用条件を「TOEICスコア〇〇点」とする企業も多くある。前者はビジネスや日常での英語力を問うのに対し、後者は学校(特に大学)でのやり取りを前提とした英語力が問われる。
英語を武器として使うのであれば、TOEICは700点以上、TOEFLは70点以上が一定の基準となる。校正技能検定:【学歴・実務経験不要】文章を校正するときに役立つ資格であり、マスメディアや編集業務、文章の著作物を扱う業界を目指す人向き。事務作業などで文章を作成する業務に就く人にも有用で、「実務経験ゼロだが、出版業界に入りたい」という人のための足掛かりとなる。
40代からの資格取得は、
新しい業界や職種にキャリアチェンジする
現在従事する業界・職種でステップアップ・キャリアアップを目指す
のいずれかによって、選ぶべき路線が異なります。40代は時間を無駄にすることができない世代です。自分のキャリアパスをしっかりと見据え、上記の資格選びのポイントを意識しながら有益な資格取得を目指しましょう。
40代でも大丈夫!資格取得を成功させる3つのコツ
40代は家庭を持っている人も多いうえ、現職でも管理職に就いていることが多く、勉強のための時間を確保することが大きな課題となります。
そこで、40代でも資格取得を成功させられる3つの心掛けをご紹介します。きちんと意識して学習を進めていけば、資格取得も決して「無理なこと」ではありません。
① 勉強を生活のなかに取り入れる
40代は多忙な世代であり、自分にとって集中しやすい時間帯や曜日を見つけ、短時間でも継続できるようなルーティンを日常生活のなかで構築することが、継続学習のコツです。
たとえば、通勤時間や昼休みを活用し、1日30分でも学習を積み重ねるなどの工夫が考えられます。オンライン教材や音声講座など、場所や時間を問わず学べるツールを併用すれば、生活リズムを崩さずに学び続けられるでしょう。
② 短時間で取得できるよう効率的な学習を心掛ける
過去問や演習問題を積極的に取り入れることで、実際の試験形式や出題傾向を早めに把握し、効率的な学習を行うことができます。教科書や問題集はある程度数を絞り、一つひとつの教材・問題に対する理解度を深めるように努めましょう。
40代で取得することになる多くの資格は、単なる暗記ではなく、実務経験を絡めて知識を応用する力も問われます。そのため、仕事や生活で得た気付きや課題を学習内容と結び付ける意識を持つと、より総合的な学習が可能となります。
③ モチベーション維持のための工夫をする
学習を続けるうえでは、「モチベーションの維持」が非常に重要です。
モチベーションを維持するためには、以下のような方法が有効です:
資格取得の目的を明確にする:「この資格を取得して〇〇業界に転職する」「資格手当の支給で〇〇を購入する」など、具体的な目標を持つことがモチベーションアップの秘訣です。「専門性を活かして社内外で頼られる存在になる」など、未来の目標を紙に書き出しておくのも良いでしょう。
小さな目標を設定する:「資格取得」が最終的な目標ではあるものの、そのために半年や一年意欲を持ち続けるのは簡単ではありません。「科目合格をする」などの小さな目標を、各段階で設けるようにしましょう。「毎日2単元を勉強する」などのように、スモールステップを設定してクリアしていくと、モチベーションの維持につながります。
仲間やコミュニティと学習体験を共有する:同じ資格取得を目指す仲間やコミュニティと、学習体験を共有するのもひとつの方法です。「直接話す」という手段に限らず、SNSなどでつながるだけでも問題ありません。
家族や職場に話しておく:家族や職場にも資格取得の意志を伝えておくと、応援してもらえたり職場でも協力してもらえたりと、前向きな気持ちを維持しやすくなります。周りから勉強についてのアドバイスがもらえたり、声を掛けてもらうことで「有言実行」を目指して頑張る意欲がアップするでしょう。
40代の転職 資格取得をキャリアで活かすヒント
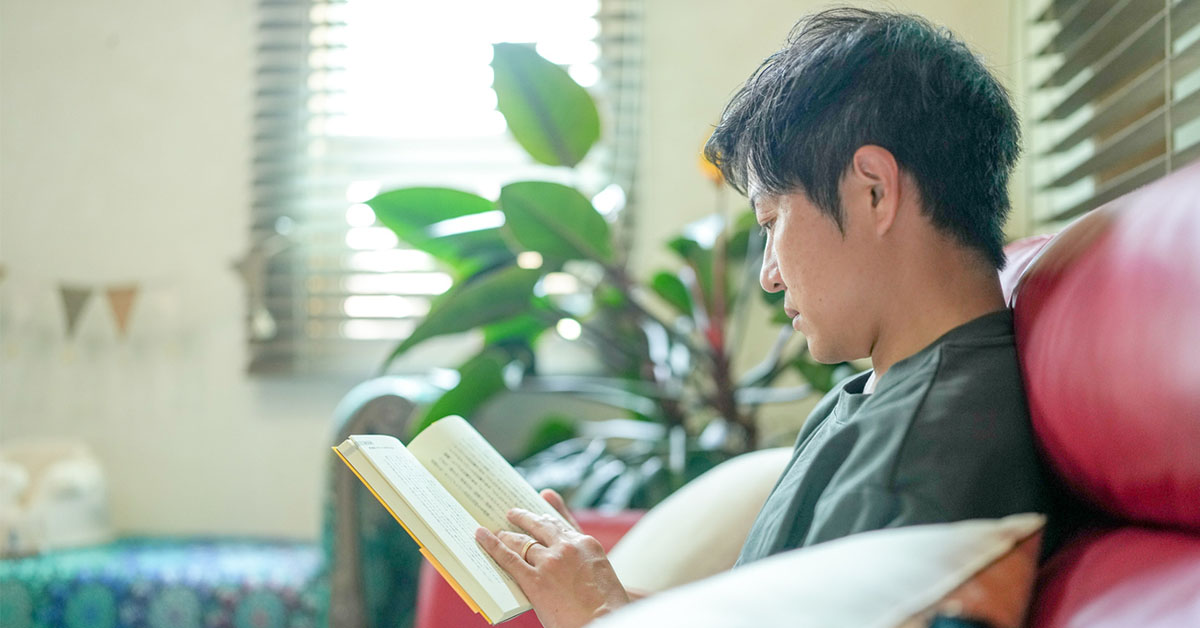
資格は、「ただ取れば良い」というものではありません。それを転職やキャリアアップに絡める視点を持つことが、40代の転職においては非常に重要です。
では、どのようにキャリアに落とし込んでいけば良いのでしょうか?以下の3つのヒントを意識してみましょう:
① 経験との相乗効果を狙う
取得した資格を活かすには、キャリアのなかで培った知識やリーダーシップ、現場での判断力と組み合わせることが不可欠です。
たとえば、管理職であればPMPやMBA、中小企業診断士などを取得することで、中核業務や経営改善等戦略的な役割を担いやすくなります。昨今は、あらゆる企業で業務効率化やDX推進のプロジェクトがありますので、管理職がITの専門資格を取得することで、マネジメントスキルを活用しながらプロジェクトの中心メンバーとして参加できるチャンスが広がります。
また、社外のセミナーや勉強会で知見を広げることで、資格で得た最新知識を実践の場に落とし込む機会も増えます。専門的な資格を持つことで、部門横断プロジェクトやコンサルティング案件など、従来の業務範囲を超えた新しい役割に挑戦できる土壌をつくることも可能になるでしょう。
② 未経験分野への挑戦や独立などキャリアの幅を広げる
資格取得は転職や昇進だけでなく、社内異動や独立、未経験職種へのチャレンジの際にも強い味方となります。医療事務や介護職員初任者研修のような資格を取得しておけば、未経験からでもキャリアチェンジしやすく、家庭との両立など柔軟な働き方を実現しやすいのが特徴です。FPや公認会計士のような独立開業が可能な資格であれば、個人事業主や起業への道も開けてきます。
また、複数の資格を組み合わせることで、より専門性のあるキャリアを構築することも可能です。たとえば、簿記やFPとIT系資格を併せ持つことで、ファイナンス部門のDX推進や会計システム導入プロジェクトのリーダーなど、希少価値の高い人材として活躍できるチャンスが広がります。
③ ビジネスパーソンとしての成長につなげる
資格取得の過程で得た体系的な知識は、日々の業務だけでなく職場での発言力や意思決定の場面でも効果を発揮します。たとえば、中小企業診断士やキャリアコンサルタントのような資格があれば、組織内でアドバイザーやコンサルタント的な役割を担えるかもしれません。
さらに、資格取得に向けた努力や経験は、今後の行動や自信のベースとなります。難易度の高い資格をクリアできたのであれば、困難な局面でも粘り強く取り組む姿勢や、自己成長への意欲を周囲に伝えられるアピールポイントになります。こうした積み重ねが、次のキャリアパスや新たな挑戦への礎となり、充実したキャリアを送れる確率を高めてくれます。
40代から一生できる仕事の特徴
40代以降の転職は、そこからの一生を決める重要な転換期となります。家庭を持っている人も多いため、原則として下記の4つのポイントを満たした転職先を選ぶことが理想です。
需要があり、長期的に安定して働ける
ライフステージに合わせて柔軟に働ける
専門性があり、社会的意義を感じられる
汎用性のあるスキルを身につけられる
① 需要があり、長期的に安定して働ける
40代から選ぶべき仕事には、社会の変化や技術の革新があっても、需要が途絶えず長期的に働ける安定感が求められます。たとえば、
地域社会に根差した仕事
専門性の高い職種
インフラ関係の仕事
健康や教育など普遍的なニーズのある仕事
などは、経済情勢や社会の変化の波に左右されにくい傾向があります。
下記のポイントにつながりますが、こうした分野では正社員だけでなく、契約社員・パートタイム・業務委託など多様な雇用形態を提供していることも特徴です。ワークライフバランスや柔軟な働き方が実現しやすい職業を選ぶ視点も、40代以降の転職では大切です。
② ライフステージに合わせて柔軟に働ける
40代は、人によってライフスタイルやライフステージ、プライベートの環境の差異が大きい世代です。そのため、現在および今後のライフステージを考えて、自分に合った働き方が選択できる仕事を選ぶことも大切です。
現在は、リモートワークやオンラインで対応できる業務も増えていますが、一方で現場を重視するポジションや企業もあります。その転職先が、無理なく自身のキャリアを継続・発展できる環境なのかを判断しましょう。
③ 専門性があり、社会的意義を感じられる
仕事はお金のために行うものですが、同時にお金のためだけに行うものでもありません。
一生続けられる仕事の多くは金銭的なメリットだけではなく、社会的な意義や責任感を伴う役割を持っていることが多いといえます。たとえば、地域の安全や生活インフラを支える仕事であったり、教育や医療、人々の幸せの向上に貢献できる仕事などは社会的意義を感じやすいうえに、年齢を重ねるごとに増す信頼や経験値が大きな強みとなる仕事です。こうした職種では、実績や人脈の蓄積が直接的に評価に結びつきやすく、転職後も中長期的なキャリアの安定につながります。
また、「これまでの経験や知識を土台にしながら、役割や働き方の幅を広げられる仕事かどうか」を考えることも重要です。
後進の育成を行える
地域に貢献できる
より責任のあるポジションで、顧客と直接やりとりができる
グローバルプロジェクトに参画できる
クロスファンクショナルなチームで専門性を発揮できる
企業経営や事業戦略に携われる
業務改善やプロセス効率化を担える
課題解決やコンサルティング業務に携われる
など、将来的にこれらの分野を担えることができれば、より働きがいを感じやすくなるでしょう。
④ 汎用性のあるスキルを身につけられる
40代以降の転職は、他者に代えられない専門性を持っていることも重要ですが、汎用性の高いスキルを磨いていくことも大切です。
たとえば、
どのような人とでもやり取りできるコミュニケーション力
業務プロセスの改善・効率化などを提案できる課題解決力
ピープルマネジメント力やリーダーシップ
プロジェクトマネジメント能力
などは、どの仕事でも求められる基礎力です。これらが仕事のなかで身につけられるかどうかも、検討材料としましょう。
また、高齢化や働き方の多様化、IT化など環境が大きく変化するなかでも、学び直しやスキルアップを継続する姿勢は、どの分野でも広く求められます。こうした点が評価される環境かどうかも、40代からのキャリアを持続的に成長させるコツとなります。
40代から一生できる仕事を見つけるコツ

「40代以降の仕事は一生を決める仕事となりうるため、転職はよく考えなければならない」としました。40代は、未経験の業界に転職するのもほぼ最後のチャンスとなる可能性も高いため、「自分が一生できる仕事」を見つけて取り組むのが現実的です。
では、「一生できる仕事」はどのように探せば良いのでしょうか。
転職の軸を明確にする
40代で一生できる仕事を見つけるには、「今後何を実現したいか」「どう社会に貢献していきたいか」という明確なゴール設定が鍵となります。
まずは、これまでの職務経験から自分がやりがいを感じた業務や責任、最も成果を出せた環境を具体的にリストアップしましょう。この作業により転職活動の軸が定まり、自分に最適な企業を選ぶ判断材料になります。
転職の軸が決まっていないと、目先の待遇だけで企業を選んでしまったり、複数の内定が出たときに決めきれず後悔してしまう可能性がでてきます。また、転職の動機を再確認することで、「現職に留まるほうが目標を達成できる可能性が高い」という結論に達することもあるかもしれません。
自分の希望と現実的な条件を見極める
転職の軸が決まったあとは、下記を明確にしながら転職で大切にしたいことと現実的な条件を見極めていきましょう。
自分の関心や価値観
得たい収入
現在および将来の生活環境
自身や家族の健康
働く場所
これらにしっかりと優先順位をつけて転職先を考えていくことで、転職活動で「迷子」になりにくくなります。また、自分自身の能力や市場評価を冷静に直視して、「自分の求める希望が分不相応ではないか」「自分を安売りしていないか」などを第三者目線で評価することも大切です。
業界・職種の将来性を多角的に分析する
業界や職種の将来性の有無を確認することも、40代の転職では必要です。
時代のニーズや地域社会の課題は常に移り変わっているため、どの分野が中長期的に需要が安定しているかを事前に調査しましょう。
具体的には、
自治体や業界団体の統計データ
人口動態や産業動向、政策の変化のチェック
ニュース等で最新技術の情報を得る
短期インターシップを利用する
地域の就労イベントに参加する
転職したい業界のセミナーを受けてみる
業界のコミュニティサイトに参加する
などの方法が考えられます。きちんと情報収集を行うことで、転職時のミスマッチのリスクも大きく減ります。
業務を実感できるよう情報収集を怠らない
本当に自分に合った職種や働き方を見極めるには、転職先の雰囲気や日常業務をできるだけリアルに実感することが効果的です。興味のある分野のセミナーやコミュニティサイト、地域の就労支援イベント、短期インターンシップなどに参加したり、同じ業界に従事する人に話を聞いたりすることで業務のリアルを体感しましょう。毎日業界情報を収集している転職エージェントに話を聞いてみるのも、非常に信頼できる手段となります。
こうした情報収集により、求人情報や資格取得だけでは見えない現場の空気や求められる人物像が明確になり、ミスマッチのリスクが減らせます。
40代の転職に有利な資格でよくある質問(FAQ)
ここからは40代の転職と取得すべき資格について、よくある質問に答えていきます。
Q. 40代で取得すべき「コスパ最強」の資格はありますか?
A. 士業はやはり強い
「何をもってコスパが良いとするか」は判断が分かれるところですが、公認会計士や税理士、行政書士などの士業はやはり非常に強い資格であり、取得したい資格のランキングで必ずといって良いほど上位にランクインします。
また、宅地建物取引士や中小企業診断士などもコスパが良い仕事として知られているほか、キャリアコンサルタントを評価する統計もあります。
Q. 40代女性が人生をやり直すために取得すべき資格には、どのようなものがありますか?
A. 状況によって異なるが、再就職しやすい資格がおすすめ
「子どもが手を離れたから、キャリアを再構築したい」「家庭と両立しながら仕事をしたい」などの場合は、再就職しやすく、勤務時間に融通が効く資格の取得がおすすめです。
資格取得までにある程度時間をかけられるならば、看護師の資格がやはり強いといえます。また、介護職員初任者研修は未経験でも3か月程度で取得できるので、「需要が尽きない業界」でのキャリアの再構築を目指すには有用です。
また、FP3級などは学歴も経験も不要で受けられるため、取得しやすい資格だといえるでしょう。これらは、家庭と仕事の両立や地域社会とのつながりを重視したい人にも向いており、年齢やブランクを問わずスタートできる点が支持されています。
Q. 40代で資格を取得することは「意味がない」といわれる理由と、取得の価値を教えてください
A. 意味のない資格はない
資格取得の「意味がない」とされるのは、資格取得=転職成功が約束されないということが背景にあります。
しかし、40代での学び直しや資格取得は、過去のキャリアと新たなスキルを組み合わせて自分の活躍の場を広げるチャンスとなります。特に、近年はリスキリングやリカレント教育の重要性が高まっており、選択肢を増やす行動自体が企業の評価やキャリアの広がりにつながったり、自己肯定感を高めることで仕事に対する満足度を高めたりします。
Q. 40代が転職に役立つスキルや資格を身につける際に注意すべき点は?
A. 「仕事で役に立つ資格か、自分が身につけたい資格か」で考える
資格やスキル選びでは、数だけを追うのではなく「仕事でどのように役立つか」「企業や業界がどんな人材を求めているか」という視点が不可欠です。
たとえば、DX推進や業務効率化が進む業界では、ITやデータ分析、プロジェクトマネジメントの知識と実務経験の組み合わせが重視されています。自分の強みを整理し、時流に合ったスキルアップを計画的に進めることが、選考での差別化につながります。
もちろん、「ずっと就きたいと思っていた仕事に挑戦するために、時間をかけて資格を取得する」という考えで取得を目指しても構いません。「自分が身につけたい資格」に関しては、学習自体が楽しめたり人生を豊かにしたりなどのメリットがあります。2つの視点のバランスを取ることが理想で、「自分が勉強したいこと」と「社会のニーズ」の接点を見つけられるかが大切です。
Q. 40代で「食いっぱぐれない」資格とはどのようなものですか?
A. 独占業務がある資格や、需要が尽きない資格は食いっぱぐれの可能性がほぼない
「食いっぱぐれない資格」としては、
独占業務がある資格(電気工事士など)
難関かつ有用な資格(士業など)
需要が尽きない資格(医療・福祉関係の資格など)
業界の構造的に、国に支えられている資格(インフラ関係の資格など)
今後需要が高まる資格(IT関係など)
が挙げられます。転職や昇進だけでなく、こうした資格を取得しておくことで将来独立ができたり、再就職が容易であったり、副業やフリーランスといった選択肢が選べたりとキャリアの幅が広がるメリットがあります。
40代からのキャリアチェンジや資格取得で迷っている場合、エイペックスが全力でサポートします。小さな疑問や不安でも構いませんので、ぜひ無料相談会でご相談ください。
40代の転職を目指すなら転職エージェントの活用が効率的
40代の転職では、即戦力であることや専門性が重視される傾向にありますが、求人の選択肢や採用基準は多様化しています。資格取得がどこまで通じるのか、どの企業やポジションで資格が重視されるのかなどは、時間をかけないとなかなかたどり着けない情報です。
しかし転職エージェントを利用することで、
自分自身の持っているスキルや経歴の棚卸しができる
自分の希望と現実的な選択肢の差を確認できる
企業ごとの内部情報や採用基準を共有してもらえる
自分の強みのアピール方法(面接・履歴書)が分かる
業界ごとの最新動向を把握できる
異業種の転職情報や、グローバル案件などの情報が手に入る
非公開案件を紹介してもらえる
内定の際、給与や条件の交渉を代行してもらえる
といったメリットが得られ、転職成功の確率が上がります。
40代以上の転職では、実績やマネジメントスキル等の伝え方にも工夫が求められるため、プロのサポートを受けることは大きな安心材料となります。
「働きながら資格取得に挑戦する」「家庭を持ちながら資格取得を目指す」という40代も多いなか、効率的な転職活動は必須です。ぜひ一度、人材コンサルタントのサポートがどのようにあなたのキャリアや転職活動の成功確率を高めてくれるのか、エイペックスの個別相談会でお確かめください。






