近年、企業法務の求人で「コンプライアンス担当者」の募集が増えています 。特に最近では、ハラスメントや情報流出等の話題でよく耳にしますが、「法務」との違いについて正確に理解できていない人も多いのではないでしょうか 。
「法務・コンプライアンス職」などまとめて求人募集されることも多いことからわかるように、両者は密接に関わっていますが担う役割はそれぞれ異なります 。近年は、「法務担当者」「コンプライアンス担当者」といように職種を分けて設置する企業も多くなっており、「法務とコンプライアンスの違い」をしっかり理解しておかないと、転職で後悔してしまう恐れがあります。
そこで本記事では、渉外事務所で長い勤務経験を持つ弁護士が 、法務とコンプライアンスの違いやそれぞれの役割、具体的な仕事内容、求められるスキル・資格から、キャリアパスや年収・求人例までをわかりやすく解説します。
目次
法務とコンプライアンスの違いとは?
企業経営にとって法務・コンプライアンスが重要な理由
法務・コンプライアンス部門の仕事内容
法務・コンプライアンス担当者に必要なスキル
法務・コンプライアンス部門で役立つ資格
【業界別】法務・コンプライアンス職の平均年収
【業界別】法務・コンプライアンス職の求人例
法務・コンプライアンス職のキャリアパス
法務・コンプライアンス業界の最新動向
法務・コンプライアンスでよくある質問
エイペックスの活用で理想の法務・コンプライアンス求人に出会える
法務とコンプライアンスの違いとは?
法務とコンプライアンスは、「企業の信頼を守る」という共通の目的を持ちながらも、担う「目的」「役割」「対象範囲」「アプローチ方法」に明確な違いがあります 。
ここで、まず両者の基本的な役割や代表的な業務を整理し、その違いを明確にすることで基礎的な理解を深めていきましょう。
法務部門の役割
「法務(リーガル)」は、その会社の事業活動や社内運営に関する「法律リスク」をコントロールする役割を担うため、法律上のアドバイスを組織に提供することが大きな役目となります。
下記は、具体的な法務業務の代表例です:
契約書等法的文書の作成・審査・交渉・締結・管理
訴訟・外部紛争・行政対応その他法的手続きへの対応、外部法律事務所との連携
取引・事業戦略等に関する法的助言の提供とリスク評価
株主総会・取締役会の運営サポート(招集手続・議事録作成・登記対応を含む)
社内規程やガイドライン等の法律的整合性の確認
特許・商標・著作権等の知的財産の管理(出願・権利侵害対応・ライセンス契約等)(知的財産部等が担当する場合もあり)
個人情報や営業秘密などのデータ・情報資産の管理
業界法規や行政規制のリサーチ・変更対応、必要な許認可の取得・維持・支援
M&A・事業提携等の法務支援(法務デューデリジェンス・契約交渉・買収後の法務統合支援等)
株式発行・合併・会社分割・事業譲渡等の組織再編・資本取引に関する法的支援(スキーム・スケジュール設計、契約書・議事録作成、登記手続等)
上場準備・IPOの支援(法的文書整備・リスク評価等)
(外資系企業の場合)グローバル方針・手続きの日本法対応・適合性確認、外資規制対応
このように、法務部門は企業のあらゆる活動における法的リスクを特定し、軽減や回避のための戦略を策定する重要な役割を担います。いわば、社内における「法律の専門家」として、リスクを回避しながら円滑な事業運営をサポートすることが使命となります。
コンプライアンス部門の役割
「コンプライアンス」は、直訳すると「法令遵守(順守)」を意味しますが 、現在は法令だけでなく、就業規則などの企業規範や内部規則に加え、業界基準・モラル・道徳といった社会規範に至るまで求められる範囲が広がっています。
つまり「法令遵守」に加え、「社会的規範や倫理に適った行動を取る」ことまでがコンプライアンスの範囲です。社内のコンプライアンス遵守体制を整えて秩序を維持し、企業の信頼性を高めることがコンプライアンス部門の大きな役割となります。
下記は、具体的なコンプライアンス業務の代表例です:
コンプライアンス体制の整備や社内規程・行動規範の策定(権限の明確化、チェックフローの確立などを含む)
内部通報窓口の運用・管理(見直しを含む)
不祥事・法令違反発生時の初動対応マニュアル・方針の策定
不祥事・法令違反発生時の対応・調査・報告、原因分析、再発防止策の検討
従業員教育やコンプライアンス研修の企画・実施・習熟度・成果の確認
コンプライアンス遵守状況の確認・リスク評価・監査
ESG(環境・社会・ガバナンス)・サステナビリティ関連の社内方針整備や開示支援
内部統制の整備・運用支援
このように、コンプライアンス部門は単なる法令遵守にとどまらず、企業全体の健全な運営と信頼性を支える重要な役割を担っています。
関連記事:コンプライアンスの仕事内容を具体例で解説|法務との違い・必要スキル・年収
両者が混同されやすい理由
法務部門は法律知識を活用し、主に個別の契約や法的トラブルの解決・予防を通じて企業を守ります。
一方コンプライアンス部門は、組織全体が法令だけでなく社会規範や倫理を遵守し、適正に行動できるよう体制や仕組みを整えることで、企業の信頼を高める役割を担います。
このように本来役割や目的が違う両者ですが、組織によっては「法務・コンプライアンス部」として一体で運営されていることがあります。特に中小企業では、法務部門がコンプライアンス業務を兼任している場合も多く、そのため「違いがあるのか?」と疑問に思う人も少なくありません。
両部門は、企業活動全体のリスクマネジメントを担うという共通点があり、連携することでそれぞれの専門性をより発揮します。これにより、強固なガバナンス体制・リスクマネジメント体制を築くという「守りの体制」を作ることのみならず、コンプライアンス意識を組織文化として定着させ、企業の信頼と成長を両立させる「攻めの基盤」へと発展させることができます。
● 法的知識の戦略的活用に焦点を置き、契約や取引について法律上のアドバイスを提供する
● 法令・規則・その他社会規範等に則って業務が行われるよう社内体制を整える
● コンプライアンス遵守の文化醸成
企業経営にとって法務・コンプライアンスが重要な理由
現在の企業経営において、法務・コンプライアンスへの取り組みは非常に重要なテーマです。
法務・コンプライアンスの果たす役割は、リスクマネジメントのみならず、企業の存続と成長にとって不可欠な役割を担っています 。下記で、両者の取り組みが重要である要因を解説しましょう。
1. 不祥事防止とリスクマネジメント
企業活動には、契約・労務・知的財産(IP)・個人情報など、さまざまなリスクが内在しています。法務・コンプライアンス体制を整備することで、このような潜在的なリスクを事前に洗い出し、問題が大きくなる前に防止することが可能です 。
万が一、法的トラブルやコンプライアンス違反といった不祥事が発生すれば、行政処分や損害賠償といった直接的な損失にとどまらず、企業の信用・ブランドイメージの失墜という深刻なダメージを受けかねません。
近年は、不祥事の発覚をきっかけに企業への社会的信頼が一気に揺らぐケースも少なくありません。報道・拡散のされ方によっては、法令等で規定された罰則以上に社会からの評価・信用の低下が企業により大きな損失をもたらすこともあります。特にSNSやオンラインメディアの普及により、かつては社内で完結していた問題が瞬時に外部へ拡散し、経営危機に発展する例も増えています。
リスクやトラブルを未然に防ぐ施策だけでなく、企業価値を長期的に維持・向上させるための戦略のひとつとして、多くの企業が法務・コンプライアンス機能の強化を目指しています。
2. 経営判断の支援
法務・コンプライアンス部門は、単に法令違反を防ぐ役割だけでなく、近年では経営判断の質を高め、リスクを最小限に抑えつつ事業を加速させる戦略的パートナーとしての役割が強まっています。
日々の取引や契約締結に加え、IPOの準備、M&Aや事業再編の検討、新規事業や海外進出、アライアンス提携等、経営陣が企業の将来を左右する重要な判断を行う局面では法務・コンプライアンス部門のサポートが欠かせません。こうした場面では法的な観点だけでなく、社会的規範や企業倫理の観点も踏まえたアドバイスが求められ、経営陣が正しい意思決定を行えるよう支援します。
適切な経営判断のためには、経営陣に対して十分な判断材料が提供されることが不可欠です。「どのようなリスクが生じる可能性があるか」「万が一リスクが現実化した場合の影響や損失額(損失予想額)はどの程度か」「実際にリスクが発生する可能性はどの程度か」といった点を説明し、「リスク分析の専門家」として、複雑な法的問題点・情報を可視化したうえで、具体的かつわかりやすく提示することが求められます。
このようなリスク分析により、経営陣はより適切な判断を下せるようになります。攻めるべき局面では意思決定を後押しし、慎重になるべき場面では一歩立ち止まって考える機会を提供します。事業推進のアクセルとリスク管理のブレーキの両面を適切に果たすことにより、企業の持続的な成長を支えられるのです。
3. 企業価値を高めステークホルダーからの信頼を確保する
投資家や取引先・顧客などの企業のステークホルダーは、企業の経営状態や財務の健全性に当然関心を持ち、意思決定の際にそれらを重視します。
近年は、「法令を守るだけでなく、倫理的に行動しているか」も企業の信頼性への重要な判断基準となっており、特にESGやサステナビリティ経営の観点からも、ガバナンスの透明性やコンプライアンス意識の高さが企業評価に直結するようになってきました。
日常的に、メディアやSNSでコンプライアンス違反の事例を目にするように、事業活動を行う以上コンプライアンス違反や不祥事はどの企業でも起こり得るものであり、体制を整備しないことは大きなリスクです。
逆にいえば、健全なコンプライアンス体制が確保されていればステークホルダーからの信頼が高まり、「投資家が安心して投資判断ができる」「取引先が安心して取引を行える」「消費者が安心して商品を購入できる」など、取引拡大に大きく貢献します。特に上場企業の場合、コンプライアンスが行き届いているかどうかは投資判断に大きな影響を与えるため、企業の価値向上に直結します。
また、ESG・サステナビリティ経営の重要性の高まりから、ガバナンスや企業倫理を専門的に扱う体制が求められるようになったことも分離の要因の一つです。 さらに、上場企業やグローバル企業では、内部統制やリスク管理体制を第三者的立場からチェックする必要があり、コンプライアンス部門を独立させることで監視機能を強化する狙いもあります。
このように、法務とコンプライアンスを分けることで、法的実務と倫理・統制の両面から企業統治をより強固にすることが目的とされています。
4. 健全な職場環境の整備による人材の安定確保
コンプライアンス体制を整えることは、企業における健全な職場環境を社員に提供することでもあります。たとえば、ハラスメントなどの問題行動に対して事前に防止策を講じることで、社員の不正行為やパワハラなどを未然に防ぐことができ、社員が安心して業務に取り組むことができるようになります。
経営層が率先してコンプライアンス遵守の重要性を示すことで、社員一人ひとりの行動規範が浸透し、組織全体の健全性も向上します。組織全体でコンプライアンス意識が高まると、単なる「ルール遵守」にとどまらずそれが企業文化として根付き、結果として社内の風通しも良くなり、職場の雰囲気改善にもつながります。
現在多くの企業が人手不足に悩むなか、こうした健全な職場環境が離職率の低下や入職希望者に対する採用時のアピールポイントにもなります。パワハラなどの不正行為に対する監視の目はますます厳しくなっているため、求職者にとってコンプライアンス意識の高い職場は非常に魅力的です。
このように、コンプライアンスの整備は健全な職場環境の構築を支えるだけでなく、人材の安定的な確保や組織の活性化にもつながる重要な取り組みといえます。
法務・コンプライアンス部門の仕事内容
上記の「法務部門・コンプライアンス部門の役割」でも触れましたが、それぞれの仕事内容について詳しく見ていきましょう。
法務部門の仕事内容
法務部門が担う役割は、法的リスクを踏まえつつも円滑な事業運営を支援することにあります。
そこで、上記でご紹介した法務業務の代表例のうち、どの企業にも当てはまる①~⑦の仕事内容を解説します。
① 契約書等法的文書の作成・審査・交渉・締結・管理:
売買契約・秘密保持契約・業務委託契約など、取引において発生する様々な契約において契約書を作成・審査したり、取引相手と契約内容について協議・締結したりする仕事であり、法務部のメイン業務のひとつです。
具体的には、契約内容に自社に不利な条項が含まれていないか、自社に有利な内容であったとしても過度に有利な場合には独占取引法・下請法・消費者法等の法規制に抵触する恐れがないかなどを検討します。また、単に有利か不利かという点のみならず、解釈の余地を生じさせないために文面のわかりやすさなどの明確化を行う必要があります。
契約書の作成・審査の主な目的は、多角的な視点でビジネスリスクを洗い出し、そのリスクを最小限に抑えることです。相手との関係においては、取引円滑化の観点も踏まえる必要があり、交渉相手とのパワーバランスなども踏まえた修正案の提示・条件交渉を行うなど、バランス感覚と調整・交渉力も求められます。特に企業活動の根幹となる事業に係る契約については、企業活動に大きな影響を与えることがないよう法的に安全な形に整えることが重要です。
② 訴訟・外部紛争・行政対応その他法的手続きへの対応:
万が一、取引先や顧客との間にトラブルが発生した場合、訴訟や調停・仲裁といった法的手段に対して、会社を代表して対応するのも法務部門の重要な役割です。
具体的には、訴訟戦略の立案や主張書面の検討、証拠として必要となる資料の作成、相手方や裁判所とのやり取りがあります。外部の法律事務所に依頼して対応することも多くありますが、頼り切るのではなく外部の弁護士と連携し、会社の意向を弁護士に伝え適切に対応してもらえるよう間に入るのも法務部門の大事な役割です。
ただ、顧問弁護士やいつもお願いする弁護士のスケジュールが合わない・利益相反などの関係で対応できない・案件によってはより専門性のある弁護士に相談したほうが良いなど、さまざまな状況が考えられます。法務部門には、外部弁護士とのネットワーキングや弁護士情報の収集なども期待されています。
また、行政機関からの調査・指導・行政処分への対応も法務部門の重要な職務です。関係部署と連携しながら、事実関係の整理、行政当局との折衝、再発防止策の検討・実施までを一貫して行うことが求められます。
③ 取引・事業活動等に関する法律相談や法的アドバイスの提供:
会社の経営陣や事業部門に対して法律相談に応じたり、法的アドバイスを提供したりすることも求められます。小規模の会社であれば外部の顧問弁護士が担当しますが、法務部門は「社内の法律顧問」として、日常的に経営や事業活動を法的な側面から支えます。
たとえば、重要な経営判断に関わる際には法的リスクを事前に調査・評価し、適切な助言を行います。新規事業の立ち上げや新しいサービスの展開など、企業が新しい取り組みを行う際にも法令遵守の観点から問題がないかを確認し、リスクを最小化するための提案を行います。
社内からの相談内容は多岐にわたり、契約内容の妥当性や知的財産・個人情報の取り扱い、広告表現が関連法規に抵触しないかなど、幅広いテーマに対応します。必要に応じて法令や判例をリサーチしたり、専門的な判断が必要な場合には外部の弁護士に意見を求めたうえで、より実務的で的確な回答・助言を行うことが求められます。
このように、法務部門は日常的にリスクを未然に防ぐだけでなく、企業活動を安全かつ円滑に進めるための心強いアドバイザーとして機能しています。
④ 株主総会・取締役会の運営サポート:
企業の内部構造や運営に関連する法的事項を扱うため、取締役会や株主総会の運営をサポートするのも法務部門の重要な業務です。具体的には、開催スケジュールの調整、招集通知や議案書の作成、法的チェック、当日の議事運営のサポート、議事録の作成・管理等を行います。
これらの業務は、会社の意思決定機関であるこれらの会議が、法律や定款に基づき適正に運営されるよう支えるためにあります。特に、手続上の瑕疵(招集手続漏れ、期間不足・超過等)が発覚すれば、事後的に意思決定の取消しや無効を主張されるリスク(訴訟リスク)が生じることになります。
取締役会では経営上の重要な意思決定が行われるため、議案内容が法令や社内規程に反していないかを事前に確認すること、また意思決定プロセスの透明性を確保し、社外取締役等が適切に情報共有を受けられるよう配慮します。近年では、取締役会の実効性や内部統制システムの運用への関与など、ガバナンスの質を高めるための積極的な支援も求められています。
このように、法務部門は単に会議運営の裏方という位置づけではなく、企業のコーポレートガバナンスを適切に機能させ、経営判断の正当性や透明性を担保し、健全な企業ガバナンスの確立において重要な役割を担っています。
⑤ 社内規程やガイドライン等の法律的整合性の確認:
企業の内部規則や社内マニュアル・ガイドライン等の法律的整合性の確認も、基本的には法務部門の仕事です。
たとえば就業規則や人事規定・給与規定であれば、労働基準法や労働関連法令に適合しているか、社内マニュアルや行動規範であれば違法な義務や禁止事項が含まれていないかなどを確認します。特に、労働基準法をはじめとする労働関連法令については、既存法律の改正・新法制定・ガイドライン改定等動きの変化が頻繁な分野であるため注意が必要です。
社内規則や社内方針の策定・改訂については法務部門が主導することもありますが、企業によってはコンプライアンス部門が対応する場合もあります。これは、規則等が法令だけでなくコンプライアンスの観点からも適正かを確認する必要があるためであり、そのためコンプライアンス部門と連携して進めるケースも多くあります。
最近では、環境配慮や人権的配慮を含むESG・SDGsなど、海外で発祥した新たな企業価値の概念が日本にも導入されるケースが多くなってきています。そのため、日本のみならず海外におけるこのような動向にも目を配り、社会的要請の変化に応じて社内規程を継続的にアップデートする機能も重視されています。
つまり、法務部門が各種法令への適合性を確認し企業活動をトラブルやリスクから守る役割を担う一方で、コンプライアンス部門が倫理・社会規範の観点から規則を確認し、企業全体において法律面・倫理面を含めたコンプライアンスが継続して守られているかのチェック・アップデートを行う機能を担っています。
⑥ 知的財産やデータプライバシーの管理:
特許・商標・著作権等の知的財産は、企業の競争優位性を支える重要な資産です。これらを適切に保護し、侵害リスクを防ぐのも法務の重要な業務となります。
具体的には、ライセンス契約や共同開発契約・秘密保持契約(NDA)など、知的財産に関する契約の作成やレビューを行います。他社の権利を侵害していないか、あるいは自社の権利が侵害された場合の対応についても、法的観点から助言や支援を行います。権利出願等の取得手続きや維持・管理も行いますが、必要に応じて弁理士や外部専門家と連携して対応します。
近年では、知的財産のみならず、個人情報や営業秘密などのデータ・情報資産の管理も重要な課題となっています。これらは流出・拡散・複製が容易であり不祥事発生の可能性がある一方、そのような事態が生じると重大な不祥事として取り上げられることも多い事案です。
特に、データの利活用が国外移転などを伴う場合には、注意が必要です。たとえば、個人情報に関しては国内の個人情報保護法のみならず、GDPR等の国際的規制への適合性を確認し、データガバナンスの観点から事業活動を支えることも法務部門に期待されています。
なお、知的財産の専門部門(IP部門)が企業内に設置されている場合、IP部門が対応することもありますが、そのような部門では主に知的財産の出願・管理等が期待されている一方で、法務部門が契約審査や訴訟対応等の法的支援を担うことになります。
⑦ 業界法規や行政規制のリサーチ・変更対応:
企業活動に関わる新たな法令やガイドライン・行政通達、またその改正等を継続的に調査し、各部門や経営陣に適切な情報を提供するのも法務部門の仕事です。それらの法令・ガイドラインの改正に応じて、社内規程や契約書を見直して改訂を提案したり、許認可要件を確認したり、具体的な遵守方法について助言したりします。
実際の運用や対応策の具体化は事業部門やコンプライアンス部門と連携して進めることが多いものの、法務部門は「法的リスクや規制の確認・解釈・助言」を中心に、企業が適法かつ円滑に活動できるよう支える役割を果たしています。
特に、AI・デジタル決済・データ利活用・フィンテック・ヘルステックなどの新しいビジネス分野では、法改正やガイドラインの改定が頻繁に行われています。こうした分野では、法令対応のスピードと正確性が事業競争力に直結する可能性が高いため、法務部門が日常的に行政機関や業界団体との情報連携を図り、最新の規制動向を把握・反映させることが求められつつあります。
コンプライアンス部門の仕事内容
コンプライアンス部門が担う役割は、企業がコンプライアンスを遵守するための体制構築と運用を行うことであり、企業の社会的責任を果たすための役割を負っています。
そこで、上記でご紹介したコンプライアンス業務の代表例のうち、どの企業にも当てはまる①~⑤の仕事内容を解説します。
① コンプライアンス体制の整備や社内規程・行動規範の策定:
コンプライアンス体制の整備や社内規程・行動規範の策定は、コンプライアンス部門の根幹をなす中心的な業務のひとつです。会社全体として法令遵守や倫理的行動を実現するための「仕組みづくり」として、基本方針や計画を策定します。これにはコンプライアンス体制の構築や担当部署の設置、内部通報制度の整備、違反事案発生時の調査・報告フロー、初動対応を想定したマニュアル・方針作成等も含まれます。
さらに、社員が日常業務で遵守すべきルールや行動指針として、社内規程や行動規範を作成・改訂します。たとえば、ハラスメント防止規程や情報管理規程、取引先との関係で守るべき行動指針(例:贈収賄防止に関する行動指針)等が含まれます。
これらの規程や規範は、法令だけでなく企業倫理や社会的規範も踏まえて策定されるため、多岐にわたる場合もあります。そして、このような規定や規範は、社員一人ひとりが判断に迷ったときの基準となります。
当然ながら、必ずしも法令に明るくない社員や、文章を読み解くのが苦手な社員もいます。そのために、コンプライアンス部門は専門用語を避けたり、想定される具体的事例を盛り込んだり、どのような人でも理解でき、行動に移せるようなわかりやすい内容を策定することが求められます。
② 内部通報窓口の運用・管理:
コンプライアンス等に関する内部通報窓口を運用・管理するのも、コンプライアンス部門の重要な役割のひとつです。
公益通報者保護法に基づき、従業員が不正行為や法令違反を安心して通報できる仕組みを整備して、通報内容の受付・記録・状況確認を適切に行います。また、通報者の匿名性や安全を確保しつつ、必要に応じて関係部署や経営陣に報告し、問題解決に向けた対応を支援します。
窓口を設置しただけでは不十分であり、それが効果的に運用されているか定期的に確認・評価し、見直しを検討することで従業員が安心して声を上げられる環境づくりを推進します。
③ 不祥事・法令違反発生時の対応・調査・報告、再発防止策の検討:
相談窓口等への報告により、不祥事や法令違反の兆候を掴んだ場合、その事実確認や関係部署・経営陣への報告、対応策の検討といった初動対応もコンプライアンス部門に求められる役割です。ヒアリングや調査を通じて真相発見を行い、そのうえで、仮に不祥事を発見した場合は、外部への流出可能性にも注意を払いつつ適切な対応策を講じる必要があります。
また、発見された不祥事に対してはこれに対処するのみならず、今後の再発防止策を講じることもコンプライアンス部門の大切な仕事です。
④ 従業員教育とトレーニング:
社内向けのコンプライアンス教育とトレーニングの提供も、コンプライアンス部門の主要な業務のひとつです。
知識の定着と意識向上を目的として、贈収賄防止・ハラスメント防止・個人情報管理などをテーマに研修を行い、全従業員が法令や社会規範を遵守することの重要性を理解したうえで日常業務において適切な行動を取るよう促します。また、法改正や社会的・倫理的規範に変更が生じた場合、内容をアップデートして教育を行います。
また、内容によっては従業員のみならず、役員等の経営者層にも研修やトレーニングを行うこともあります。経営層が率先してコンプライアンスを遵守することにより、社内全体にコンプライアンス重視の文化が根付くため非常に重要です。経営者層のコンプライアンス違反は、従業員の違反よりも社会に与えるインパクトが大きいということを認識しなければなりません。
⑤ コンプライアンス遵守状況の確認・リスク評価・監査:
コンプライアンスの遵守状況をモニタリングすることも、コンプライアンス部門の重要な業務のひとつです。企業によっては、コンプライアンス体制を構築することに主眼をおき、設置して満足してしまうケースもあるからです。構築した体制が有効に機能し実効性を有するかチェックしたうえで、定期的に見直すことによってはじめて意味を成します。
そのため、社内の各部門の事業活動や業務プロセスが法令や社内規程・行動規範を適切に遵守しているかを定期的に確認し、業務上発生し得るコンプライアンスリスクを洗い出し、その影響度や発生可能性を評価します。リスク評価の結果をもとに、優先度の高い課題に対して改善策や監督方針を提案することも求められます。
モニタリングには定期的な監査の実施も含まれ、コンプライアンス体制や内部規程の運用状況を評価・報告します。監査結果は経営陣や関係部署にフィードバックされ、必要な改善策の策定や社内教育に活かされます。
また、これらの前提として、コンプライアンス部門が現場の実態を把握できているか、コンプライアンス部門に報告しやすい状況となっているかという観点からの見直しが必須となります。「コンプライアンス部門がチェックをしている」「コンプライアンス部門が話を拾ってくれる」という認識が企業内に生じることで、コンプライアンス部門への信頼も高まり、社員の遵守意識も向上します。
こうした業務を通じて、コンプライアンス遵守の徹底とリスクの未然防止、企業全体の健全な運営を支えています。
企業によっては法務・コンプライアンス部門を分けない
前述のように、近年は「法務部」「コンプライアンス部」と機能を分けて運営する企業が多くなってきましたが、中小企業やスタートアップでは、リソースや人手不足から「法務・コンプライアンス部門」として両方の業務を同じ担当者が兼務するケースが多くあります。
両方の機能を一体化して運営するメリットは、情報共有や意思決定のスピードが速くなる点です。法務の視点から契約や取引の法的リスクをチェックしながら、同時にコンプライアンス上のリスクや社員教育までを一貫して管理できるため、連携ミスや伝達ロスを減らすことができます。
一方で、専門性が分散してしまうというデメリットも存在します。法務業務とコンプライアンス業務は共通する面もありますが、求められるスキルや視点・知識が異なるため、担当者の負荷が増えやすくなります。そのような状況では、特定分野の深い知識や高度な戦略立案に対処することが困難となり、企業内のリスクを見落としてしまう可能性が出てきます。
そのため、大企業やグローバル企業では法務とコンプライアンスを分け、専門的な運営を行うことが多いのですが、重要なのは法務・コンプライアンスいずれの業務も抜け漏れなく社内において機能させることにあります。
法務・コンプライアンス担当者に必要なスキル

法務・コンプライアンス担当者には、法律知識だけでなく企業全体のリスク管理や倫理の浸透を担うため、総合的な能力が必要です。
以下は、法務・コンプライアンス担当者に求められる代表的なスキルです。
法律・業界慣行への理解
コミュニケーション力・交渉力
リサーチ能力
分析力
IT・リーガルテックへの理解
法律・業界慣行への理解
まず、基礎となるのは「法律知識と規制への理解」です。
民法・商法・会社法・労働法・知的財産法・個人情報保護法など、多くの会社でも適用が検討される法律への理解に加えて、自社の事業に関連する業界ごとの個別法律を理解することが必須です。
また法律のみではなく、官公庁や自主規制団体が定めているガイドラインや業界慣行・独自の業界ルールについても理解を深める必要があります。
このような分野に対する正確な知識は、法務・コンプライアンス担当者が業務を行ううえで前提となる知識です。正確な知識を持ちつつ、状況に応じた運用と判断を行い、法的リスク・コンプライアンスリスクを未然に防ぐことが求められます。
コミュニケーション力・交渉力
法務・コンプライアンスの担当者は社内外でさまざまな関係者・部門と関わることになり、「コミュニケーション力や交渉力」が非常に重要です。
契約や取引・業務プロセスに関して現場の担当者とやり取りが発生するため、法的リスクやコンプライアンス上の問題をわかりやすく伝えるスキルが必要です。単にルールを示すだけでなく、相手が納得し理解できる形で説明することが求められます。
また、重要な経営判断の場面では、経営陣に対してリスクや法的観点を適切に報告し、意思決定の判断材料として活用してもらうための説得力のある説明能力も必要になってきます。さらに、契約交渉や取引先対応・訴訟対応・行政との調整など相手方や外部弁護士とのやり取りでも、生じうるリスクを最小化するため高いレベルでの交渉力が求められます。
コミュニケーション力は口頭でのやり取りだけでなく、契約書や社内規程等の作成においてわかりやすい文書を作るという場面でも必要になります。また、相手によっても使い分けが必要で、自社の従業員であれば明解で円滑なコミュケーションが求められる一方、訴訟相手や経営陣に対するリスクの指摘などの場面では、企業の利益のために言及すべきことを臆せずに伝えられるかが重要になります。
リサーチ能力
「高いリサーチ能力」も非常に重要です。
企業活動は多様化・複雑化・グローバル化が進んでおり、最新の法令などの改正や規制動向・業界ガイドライン・コンプライアンスの視点で社会から求められていることについて、常にリサーチを重ね情報収集を行う必要があります。法令や規制は頻繁に改正されるため、最新の動向をキャッチアップし社内のルールや契約書への反映を検討することも求められます。
また、社内で発生した問題において先例がないというケースも日常的に生じます。その際には、アクセスできる情報から参考となる事例等をリサーチする必要があります。このような高いリサーチ能力があって、法的・コンプライアンス的なリスクを洗い出すことができ、適切な対処方針を検討することができます。リサーチ能力は、正確で信頼性の高いアドバイスを行うための基礎であり、企業のリスクを最小限に抑えるために欠かせないスキルといえます。
分析力
複雑な情報を整理し、リスクや課題を的確に見極める「分析力」も重要です。審査する契約書のなかで何が問題になるのか、相談内容で解決しなければならない問題は何かなど、表面的な内容だけでなくその背景事情までを理解し、問題点やリスクの発見につなげます。つまり、個別の案件ごとに深い分析を行うことによってはじめて、実効性のある回答や対応策が検討できるのです。
また、コンプライアンスの分野では不祥事の兆候を早期に察知するために、情報収集力やデータ分析力も必要であり、リスクが発見されたときにはその他の問題はないかといった想像力を働かせることも重要です。
このように、情報を集めたあとに内容を多角的に整理し、法的・倫理的観点から課題を抽出して経営判断の材料につなげられる分析力は、法務・コンプライアンス担当者の中核的な能力といえるでしょう。
IT・リーガルテックへの理解
近年、契約管理システムやAIによる法令検索・契約レビュー支援など、リーガルテックサービスの活用やデジタル技術の導入が活発化しており、法務業務の自動化・効率化が進んでいます。担当者にはこれらのツールを適切に活用することが求められ、ITリテラシーやシステムへの理解が必要不可欠となっています。
これまで手作業で行っていたルーティン業務が自動化したことで、法務担当者はビジネスの成長に直接関連する戦略的な案件に集中できるようになりました。つまり、デジタルツールを使いこなすことは業務の効率化や正確性を高めるだけでなく、法務部門がより価値ある提案を行うための基盤を築くことにもつながります。
今後の法務部門には、一定のITリテラシーと法務知識を兼ね備えた人材がますます求められるようになるでしょう。
法務・コンプライアンス部門で役立つ資格
法務・コンプライアンス部門では弁護士以外の担当者も多く活躍しますが、今後業務を行っていくうえでどんな資格が役立つのでしょうか。
下記に役立つ資格の例を挙げましたので、参考にしてみてください。
法務全般で役立つ資格
中小企業診断士:中小企業の経営課題を診断し、改善策を助言する経営コンサルタントの国家資格。経営全般やリスクマネジメントなど企業の事業活動に関する知識が身につくため、法務・コンプライアンスの視点だけでなく、経営戦略とリスク管理を統合的に考える力を養える。
ビジネス実務法務検定試験(2〜1級):東京商工会議所が主催し、「企業法務の知識をビジネス実務に活かすこと」を目的とする民間試験。2級が実務担当者レベル、1級が管理職やリーダーレベル。
行政書士:官公庁に提出する書類作成や許認可申請、契約書の作成などを行える国家資格。法務に関する専門知識を活かせるため、法務部で契約書作成や法令対応などに携わることができる。
証券アナリスト:公益社団法人日本証券アナリスト協会(SAAJ)が認定する資格。金融業界で高く評価される資格だが、企業の財務状況や価値を分析する専門知識を有するため、M&Aや企業再編などの法務案件においても価値が高い。
コンプライアンス・内部統制・内部監査で役立つ試験
公認内部監査人(CIA):CIAはCertified Internal Auditorの略称で、日本内部監査協会が認定する世界基準の資格。内部統制や監査の知識を体系的に学べ、コンプライアンス体制の整備・運用、内部通報制度の運用などに直接活かせる。内部監査人としての能力・専門性が証明できるだけでなく、会計やファイナンスなど経営者の意思決定の礎となるビジネス知識も含まれているため、経営者の視点も養える。
認定コンプライアンス・オフィサー:一般社団法人コンプライアンス推進機構(OCOD)が主催する民間の試験。組織のコンプライアンス態勢を整備・機能させるために主導的な役割を担うハイレベルの専門家として、コンプライアンスの実現に必要となる内部統制・企業法務等に関する幅広い知識・判断力を養える。
個人情報保護士:個人情報保護法の施行に伴い導入された民間試験。個人情報保護法だけでなく、組織における個人情報の取り扱いに関するガイドラインや運用の仕方・管理規程などを体系的に学べる。
弁護士資格があれば法律面での専門性は保証されるため、転職などで優遇されることに変わりはありません。弁護士以外の方は、実務や特定分野における信頼性・説得力を高めたり、継続的な自己学習をアピールしたりするために、資格を取得する価値は十分にあるでしょう。
【業界別】法務・コンプライアンス職の平均年収
下記は、インハウス弁護士として活躍される413名のエイペックス登録者の方を対象に、各業界ごとに給与額を分析した平均総報酬額のデータです。
*総報酬額=基本給+目標賞与
業界により幅はありますが、インハウスポジションの場合、多くの業界で平均年収が2,000万円以上となっています。業界だけでなく、企業の規模、外資系・内資系、職位などにより年収額は異なり、転職では個人の経験やスキルによりオファー金額も変わってきます。
詳しい求人動向や自身の市場価値の判定については、ぜひエイペックスの法務・コンプライアンス専門のコンサルタントにご相談ください。あなたの経験や志向から、あなたの人材としての価値を最大化できる案件をご紹介します。
【業界別】法務・コンプライアンス職の求人例
では、実際に現在の転職市場ではどのような法務・コンプライアンスの求人募集があるのでしょうか?
下記は、エイペックスでの最新の求人募集の抜粋です。業界別に分けましたので、今後の転職やキャリアの方向性の参考にしてみてください。
洞察提供者:
佐々木 愛
Apex法務・コンプライアンスチームに所属するシニアコンサルタント。大手・外資系法律事務所のみならず、金融からリーガルテックまで幅広いインハウスポジションを担当。丁寧なコミュニケーションと一貫したサポートにより、事務所・事業会社ともに多くの紹介実績を持つ。
IT業界
金融・保険業界
製薬業界
医療機器業界
製造業界
その他の業界
法務・コンプライアンス職のキャリアパス
ここで、法務・コンプライアンス職で考えられるキャリアパスを見てみましょう。
あくまでも一例ですが、企業では豊富なキャリアパスが用意されていることがうかがえます。
1. 初期キャリア(入社〜3〜5年)
ジュニアインハウスカウンセル /アソシエイトレベル
弁護士資格取得後、一般的には法律事務所に入所。その後3〜5年の経験を経てLL.M.取得のため米国や英国に海外留学することが多い
近年では、弁護士資格取得後のファーストキャリアとして企業に入社するケースも徐々に増えている。これは、若い世代のワークライフバランスへの意識の高まりが影響していることが考えられるインハウスの場合の業務内容
契約書の作成・審査、取引リスクのチェック、社内の現場担当者からの法務相談の対応など
部署間の調整や内部規程の理解のほか、外部の法律事務所との協業も並行して学ぶ必要スキル
契約法、会社法、労働法などの実務知識、社内調整力、基本的なコンプライアンス知識
2. 中堅キャリア(5〜10年)
シニアインハウスカウンセル/法務・コンプライアンス担当マネージャー
業務内容
契約・訴訟・規程整備などを統括
法務チームのマネジメントや後輩の指導も担当
経営層に対する法的リスクやコンプライアンスリスクの助言
場合によっては、上場準備や重要プロジェクトに伴う法務課題の対応といった複雑な業務を担当
他チームとの連携、部門方針整合性の確認・是正必要スキル
リスクマネジメント力、交渉力、経営層への提言力、英語力、海外の法務知識、ピープルマネジメント力
3. 上級キャリア(10年以上)
法務部長/コンプライアンス部長/チーフリーガルオフィサー(CLO)
業務内容
部門全体の戦略・方針策定を担当
会社のガバナンス体制の整備
企業全体のコンプライアンス体制の構築・運用の統括
M&A・業務提携等の重要案件に関する経営判断に直接関与
グローバル本社や海外子会社との連携必要スキル
経営視点、ビジネス・リスクのバランス能力、ステークホルダーマネジメント能力、組織運営力、危機管理能力、マルチタスク能力、英語力、交渉力
4. 法務・コンプライアンス部門以外のキャリア
経営企画・ガバナンス・リスク管理部門への異動
経営企画やガバナンス、リスク管理部門へのキャリアチェンジも有力なキャリアパスのひとつです。
法務・コンプライアンスで培ったリスク分析力や法的思考力を活かし、企業戦略や経営判断の妥当性を法的・倫理的観点からサポートする役割を担います。
具体的には、経営計画の立案、新規事業やM&Aの法的リスク評価、内部統制・ガバナンス体制の強化など、経営の中核に関わる業務に携わることができます。独立・顧問弁護士/コンサルタント
独立して社外弁護士・顧問弁護士へのキャリアチェンジも考えられます。
顧問弁護士になると、複数の企業に対し契約書のレビューや法務相談、コンプライアンス体制の構築支援などを行うことが考えられます。企業での実務経験を持つことで、単に法律知識を提供するだけでなく、業界特有の慣行やビジネス実態を踏まえた実践的な助言ができる点が強みです。
また、近年はスタートアップや中小企業を対象に、外部顧問としてリーガルリスクマネジメントを支援するコンサルタントとして活躍するケースも増えています。グローバル企業の本社・海外拠点勤務
外資系企業のグローバル本社や、日系グローバル企業の海外拠点に駐在するキャリアも考えられます。
海外法務や国際コンプライアンス案件を担当し、各国の法規制や文化を理解したうえでリスク管理や契約交渉を行います。海外子会社のガバナンス体制の整備、現地法務担当者や外部弁護士との連携、グローバルポリシーの策定などを担うこともあります。
また、英語力や異文化コミュニケーション能力が求められるため、LL.M.留学や現地でのプロボノ経験が役に立つ可能性があります。
法務・コンプライアンス業界の最新動向
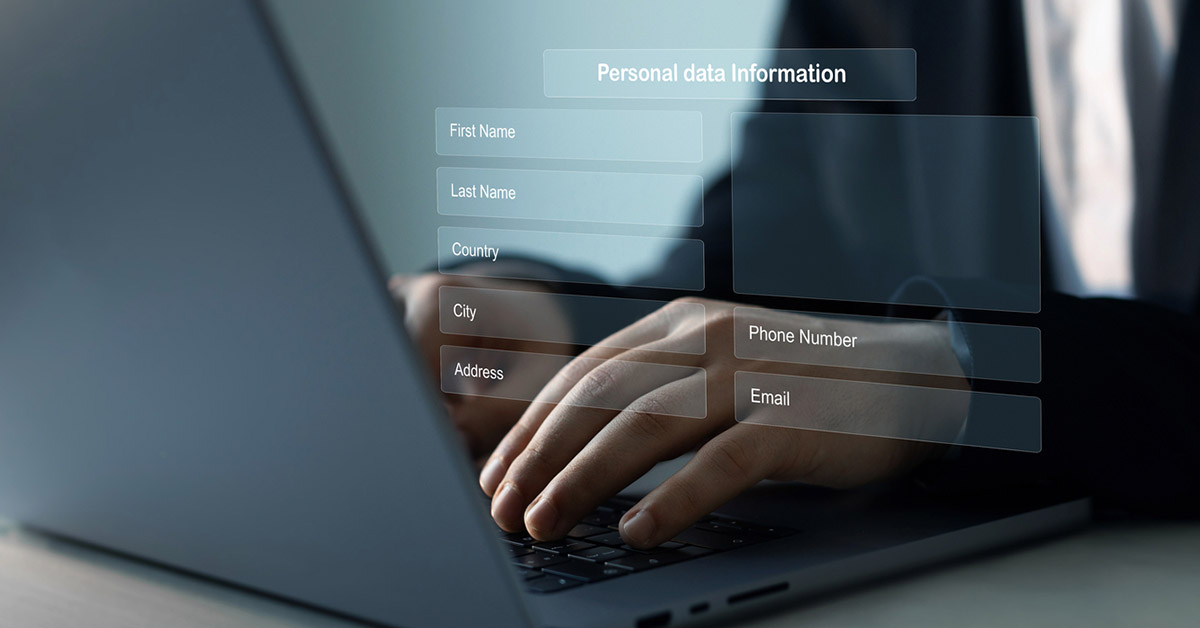
法務・コンプライアンス業界は、一般に考えられる以上に変化の激しい業界です。特に注意すべき分野のほか、求められる役割や対応しなければならないスキルも常に変化していますので、法律に携わる者としてリサーチを怠らないようにしましょう。
個人情報保護法の改正
2022年の改正以降、個人データ管理の厳格化が進んでいます。法務・コンプライアンスの担当者は、プライバシーポリシーの整備や社内教育を強化する必要があります。
また、通称「GDPR」と呼ばれる、EU(欧州連合)の個人データ保護に関する法令である「一般データ保護規則(General Data Protection Regulation)」にも注意が必要です。日本の企業において海外の個人情報を扱う可能性がある場合適用の可能性があり、違反すると罰則の適用もあります。
内部通報制度(公益通報者保護法)の改正
「内部通報制度」とは、企業内における違法行為などの通報を促すため、社内において通報窓口を設置したうえで通報者を保護する制度です。公益通称者保護法の改正(2022年6月施行)により、従業員300人超の企業では内部通報対応窓口の設置が義務化されました。
内部通報制度を導入すると、社内における違法行為・不祥事を早期に発見することができ、これに迅速に対処することでより大きな問題となることを未然に防くことができます。役員や従業員による違法行為が明るみになると、会社が刑事罰や行政処分などの対象となるほか、社会的な評判も失墜してしまいます。内部通報制度の導入は、このようなコンプライアンス上のリスクを回避する観点から効果的です。
ただし大事なことは、制度を導入して実装することのみならず、それを適切に運用できるかという点になります。
ESG・サステナビリティとコンプライアンス
近年、投資家は会社の業績や財務的な状況に加え、非財務情報についても重視する傾向にあります。特に法令遵守だけでなく、ESGやSDGsについても企業が考慮し、企業活動の持続可能性を高める経営を行っているかという視点も重要になってきました。
コンプライアンス部門には、ESG・サステナビリティ経営の実務面を支える役割を担うことが求められています。企業活動において環境規制や法令が遵守されているか、ダイバーシティ&インクルージョンが推進され労働法規や人権が守られているかなど、法令遵守のモニタリングや倫理意識の浸透を図り、健全な職場環境の維持に貢献しなければなりません。
このように、投資家や取引先、社会全体からの信頼を獲得するためESG・サステナビリティ経営の実行をリーガル・コンプライアンス面から支え、企業が長期的に健全運営ができるようサポートすることが求められています。
リーガルテック・AI活用による法務業務の効率化
上記でお伝えしたように、法務・コンプライアンス分野においてもAI化・IT化が進んでおり、法務業務を効率化・高度化するためのITツールやシステムを各社が積極的に導入しています。契約書管理、法令検索、リスク評価、コンプライアンス管理など、従来手作業で行っていた業務がデジタル化・自動化されつつあり、業務内容やプロセスの変化スピードが速いと感じる人も多いでしょう。
リーガルテックやAIの活用は効率化の手段というだけでなく、法務・コンプライアンス部門が経営の意思決定を支える戦略的パートナーとしてより機能するための重要な手段です。担当者には変化する業務フローに柔軟に対応する能力や、データ・分析結果を判断に活かす能力が必要とされ、これにより戦略的な意思決定の支援や企業価値向上により貢献できることが求められています。
法務・コンプライアンスでよくある質問
ここで、法務・コンプライアンスについて疑問に持たれることの多いよくある質問を見てみましょう。
Q. 法務とコンプライアンスは何が違うのですか?
A. 法務は主に法律リスクの管理を担い、契約書の作成・審査や訴訟対応、知的財産管理などを行います。
一方でコンプライアンスは、法律の遵守だけでなく、社会的規範や企業倫理の順守まで含めた組織全体の仕組みづくりを担当します。両者は役割が異なりますが、共通することも多く、連携することで企業の信頼性を高めます。どちらも、会社の事業活動において欠かすことのできない機能です。
Q. 法務からコンプライアンスへキャリアチェンジは可能ですか?
A. 法務の経験は、コンプライアンス分野でも大きな強みとなります。法律知識を土台に、組織マネジメントやリスク管理の経験を積むことでキャリアを広げることができます。
法務とコンプライアンスは、それぞれ別々に動くよりも連携することにより、企業のリスクマネジメントにおいてより有効な取り組みとなります。法務出身のコンプライアンス担当者は、法務とコンプライアンスの双方の視点から業務に取り組むという役割が期待されるでしょう。
Q. 未経験から法務・コンプライアンスへの転職は難しいですか?
A. 「法務・コンプライアンス職」という求人募集は、必ずしも弁護士資格が必須ではありません。しかしながら、業務未経験者が法的知識を身につけるには困難なこともあり、時間がかかることもあります。そのため、上記に挙げたような有効な資格を取得するなどして、事前に法的な素養があることをアピールできると良いでしょう。
一方で、法務・コンプライアンス分野は法的な知識さえあれば業務遂行が可能というわけではありません。わかりやすく簡潔な文書の作成能力、他部署との調整力、外部との交渉力、事業展開の拡大に伴う英語を含めた外国語能力なども高く評価されます。
加えて、法務・コンプライアンス職には現場への理解や円滑なコミュニケーションも求められます。よくあるケースですが、事業部などの現場経験がない法務・コンプライアンスの人員が対応すると、現場の部門からは「法務・コンプライアンス部門は、現場をわかっていない」と批判を受けることもあります。
そのため、未経験であっても上記のような役立つ知識・スキルを磨きつつ、現場の事業部門での経験や理解があれば、十分に法務・コンプライアンス部門で活躍できる可能性があると考えられます。
Q. 法務・コンプライアンスの仕事は今後どう変わりますか?
A. AIやリーガルテックの導入で契約書レビューやリスクチェックの効率化が進みます。
また、ESGやサステナビリティ経営の重要性が高まるなかで、コンプライアンス業務は企業戦略との関わりが増しており、経営に近いポジションで活躍するケースが増えています。
企業活動の様々な場面で、法務・コンプライアンスへの意識が高まっているため、より活躍の幅が広がるとともに、他部門への理解がより求められるでしょう。
エイペックスの活用で理想の法務・コンプライアンス求人に出会える
法務部門とコンプライアンス部門の違いや、それぞれにおいて求められる役割・具体的な業務内容・年収・求人例・業界動向等について解説をしました。
このような両者の違いなどを踏まえて、自身が法務に携わりたいのか、コンプライアンスに興味があるのか、また、自分はどちらに向いているか、どちらであればより評価されやすいかを考えてキャリア形成を行っていきましょう。
一方、転職においては企業側が応募者に何を求めているのかをしっかりと読み解くことも大切です。特に「法務・コンプライアンス担当者」の募集の場合、企業がより重視するスキルや経験がどこにあるのか見極めが必要です。
また、その求人が欠員補充の募集なのか、事業拡大による新設ポジションなのかによっても応募者に求める役割が異なります。そのほか、事業部などの現場経験のある人を求めているのか、特定の分野(個人情報、知的財産など)の法的な知見を有する人を求めているのかなどについても、見極めが必要です。
自身の希望とマッチする転職先、またその企業が求める人物像に本当に自分が適合しているのかを判断するのは、意外と難しいものです。第三者から適切なアドバイスを受け、戦略に基づいた転職活動を行う必要があり、そのため法務・コンプライアンス業界に特化した転職エージェントのサポートが欠かせません。
法務・コンプライアンス専任チームを有するエイペックスでは、一般的な求人サイトにはない非公開求人やハイクラス求人を多数取り扱っており、あなたの経験や強み・希望に合った企業を厳選して紹介してもらうことができます。日英で履歴書の作成や面接対策のサポートも提供してくれるため、特に転職未経験や、はじめてインハウスポジションを目指す場合、外資系企業を視野に入れる場合には心強い味方となります。
転職において重要なことは、自身のキャリアに対する希望を明確化し、それが実現できる企業にアプローチをしてミスマッチを減らすことにあります。今後の法務・コンプライアンスでのキャリアについて相談されたい方、最新の業界情報をご希望の方は、ぜひエイペックスのキャリア相談会にお越しください。






