スタートアップ企業にとって、採用する人材は事業の未来やプロジェクトの成功の可否そのものを決定づけるものですが、反面リソースやノウハウの不足、ブランド力に頼れないなど多くの課題を抱えています。
限られたリソースのなかでもより良い人材を確保するためには、よくある悩みや失敗を把握したうえで、「迅速に」「費用面も考慮し」「優先順位をつけて」、戦略的に採用活動を進めていく必要があります。
そこで、外資系・日系企業のハイクラス人材の採用を専門とするエイペックスが、そもそもなぜスタートアップの採用が難しいのか、限られたリソースでも実践できるスタートアップの採用戦略と成功のポイント、スタートアップに適した採用手法について、実例に基づいて解説します。
スタートアップの創業者・人事責任者・採用リーダー、そして現場を率いるマネージャーの方はぜひ参考にしていただき、組織の最重要ミッションである採用を成功させましょう。
目次
スタートアップの採用はなぜ難しいのか?
スタートアップの採用でよくある悩み
スタートアップの採用を成功させる7つの戦略
スタートアップが求める人材像と採用基準
スタートアップの採用でよくある失敗
スタートアップに適した採用手法まとめ
スタートアップ採用面接アドバイス:エイペックスのコンサルタントが語る【動画あり】
エイペックスでのスタートアップの採用成功事例
スタートアップの採用で大切なこと
スタートアップの採用はなぜ難しいのか?
そもそも、なぜスタートアップは大企業や老舗企業に比べ、採用に苦戦する傾向にあるのでしょうか?
それには、
知名度不足
マイナスイメージの先行
リソース不足
即戦力人材の確保の難しさ
の4つが主な要因であると考えられます。
知名度不足:スタートアップは広報活動にコストをかけられません。大企業に比べ知名度やブランドイメージに乏しく、事業内容が認知されていないため採用をかけても人が集まりづらいというハンデがあります。
また、事業の将来性や経営の信頼性・企業カルチャーも伝わりづらく、選考途中で他社を選ばれてしまうケースも多く見受けられます。マイナスイメージの先行:スタートアップは社内規定が定まっていないことも多く、待遇や労働時間が不透明というマイナスイメージがつきまといます。事実はどうあれ、「スタートアップはハードワークで労働時間が長い」という一般的なイメージがあり、転職希望者にマイナスに作用しています。
また「知名度不足」ともつながりますが、人は何度も触れたものに対して好意的な感情を抱く傾向にあり、候補者側からの接触回数が非常に少ないスタートアップは、好意的な印象を持たれることが少ないという不利な戦いを強いられます。リソース不足:スタートアップは常に人出不足の状態にあります。採用専任の社員を抱えることは非常に難しく、採用担当者がいたとしても少人数体制かつ他業務と兼任であることも珍しくありません。採用体制が不十分なため候補者に迅速かつきめ細やかな対応ができず、自社に対する信頼度を高められないまま他社に優秀な人材を奪われてしまうことも多々あります。
即戦力人材の確保の難しさ:スタートアップは新入社員を育成する時間や体制が整っておらず、即戦力人材を採用せざるを得ません。当然、こうした優秀な人材はより高年収・好待遇のオファーを出す他社からも引き合いがあるため、なかなか採用につながりにくい現実があります。
なお、後述しますが即戦力人材のみを採用していくと、社員の育成環境が整いにくいというマイナス点もあります。
このように、スタートアップには知名度の高い企業や老舗企業、潤沢な予算や社員を抱える企業に比べて、採用活動が不利になりやすいという課題があることを理解しておきましょう。
スタートアップの採用でよくある悩み
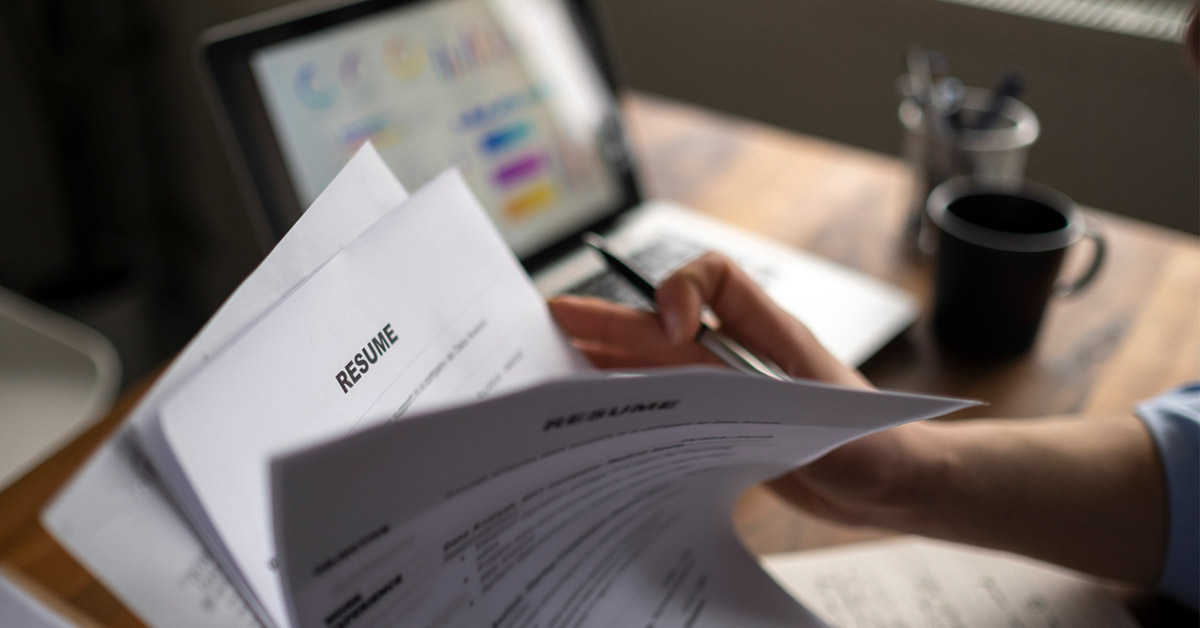
スタートアップの採用の難しさは、知名度不足やマイナスイメージ、リソースの不足、他社との獲得競争に要因があるとお伝えしました。
そこで、採用が難しいといわれる原因をふまえ、採用活動の段階ごとで担当者が抱えがちな悩みと課題についても確認していきましょう。
求人情報作成段階
「欲しい人材が集まらない」という問題は、求職者側だけでなく企業側に原因がある場合があります。求人情報を作成する段階で採用側に以下のような課題があると、募集がうまくいかない可能性が高いでしょう。
採用したい人物像が明確にできない:漠然と「即戦力が欲しい」「新しい発想ができる人がほしい」などのように思うだけで、「どのようなスキルが必要か」「どのような経歴を持った人が望ましいか」を関係者間でディスカッションができていないケースです。この点を曖昧にしたまま求人募集すると、条件だけで候補者が集まりミスマッチが起こりやすくなります。
企業の魅力をうまく伝えられない:ビジョンやカルチャーが伝わりづらいという問題は、スタートアップの抱えるもっとも大きな問題です。競合他社の求人情報が転職市場に溢れるなか、「他社にはない自社独自の魅力」が明確に打ち出された求人票なしでは、自社にマッチした質の高い人材からの応募を増やすことはできません。
求人情報の作成に時間を割けない:スタートアップはリソースが少ないため、常に時間に追われています。特に創業直後は非常に忙しく、資金集めなどに奔走させられるなか、時間のかかる求人情報の作成に苦戦する企業は決して少なくありません。
募集段階
募集段階では、まず「そもそも人に知られていない」ということが大きな重しとなってのしかかります。
求人広告や採用広報にかける予算が限られている:転職サイトなど効果的な媒体を使えず、ターゲット層に広く届きにくいという問題がよくあります。
応募者が集まらない: 知名度やブランド力が低く、求人への反応が少ないという悩みはスタートアップが共通して持つものです。単なる業務内容や条件の羅列ではなく、企業独自の魅力や仕事のやりがい、どんな未来を描けるのかなど、候補者が魅力的だと感じる情報が足りていない可能性があります。
募集要件に合った人材が来ない:即戦力人材を求めているのにスキルや経験がマッチしない応募が多く集まり、選考が難航するケースがよくあります。このミスマッチは単に選考の工数を増やすだけでなく、本当に求める人材を見逃してしまうリスクにもつながります。
「ターゲットになる人に届きにくい」「届いたとしても反応が少ない」「反応があっても募集要件にマッチしない人が多い」という三重苦は、他の段階のとき以上に採用担当者を苦しめます。
選考段階
選考段階で起こりがちなのが、「リソースの欠如」「採用基準に問題が起きる」という状況です。
採用専任者が不在などリソース不足:スタートアップでは採用担当者が不在で、経営者や事業責任者、現場の責任者などが本業の合間に採用活動を行っていることがよくあります。そのため選考プロセスに遅れが生じるなどして、候補者に「この会社は大丈夫だろうか」という不安を与えることになり、優秀な人材が離脱してしまう原因となっています。特に売り手市場の現在の転職市場では、雑ともとれる企業の対応は致命的な問題です。
採用基準が曖昧で選考に迷いが出る:本業が忙しく候補者と十分なコミュニケーションが取れなかったり、関係者間で求める人物像が一致していないと採用基準が曖昧になります。これにより選考の工数が増えて時間がかかったり、せっかく採用してもミスマッチが起こり早期退職につながるリスクが生じます。
いわゆる「スーパーマン」を求めてしまう:スタートアップは即戦力を必要としており、一人で多くの業務をこなせる人材を求めます。そのため、応募者に対して「スーパーマン」であることを求めがちで、結局採用に至らないということもあります。要件に優先順位をつけず、すべてを満たす人を求めることで有能な人材を逃してしまう可能性が生じます。
選考段階でのこれらの問題は、実際に候補者の選考に至る前までに、自社が求める人材のスキルとレベル、優先順位を関係者間で明確にすることである程度解消できます。
内定後
せっかく良い候補者がいて内定を出しても、以下のような問題が生じるため採用担当者の悩みは尽きません。
内定辞退が多い:応募者は多くの場合、並行して就職・転職活動をします。優秀な人材は複数の会社から内定を獲得するため、知名度に劣るスタートアップは他社との人材獲得競争に負けてしまい、なかなか内定承諾につながらないとう問題が起こりがちです。
条件交渉が上手くいかない:スタートアップは報酬パッケージや評価の基準がまだ確立されていないこともあり、給与や評価制度が不安定だと感じる求職者もいます。せっかく内定を出しても条件交渉で決裂することもよくあるため、不確実性を上回るだけの成長機会や事業への共感をより強く訴求する必要があります。
リファレンスチェックまで手が回らない:内定後のミスマッチを防ぐ有効手段のリファレンスチェックですが、それを行うための時間・人手が足りないという問題はよく起こります。外部に委託する場合はコストがかかるのと、そもそもリファレンスチェックの必要性の見極めや認識の共有に時間がかかるという問題もあります。
内定者フォローが手薄になる:内定者とは継続的にコミュニケーションを取り、入社意欲を高めたりミスマッチや早期退職を防ぐ施策が必要ですが、慢性的な人手不足のため内定者フォローが後回しになりがちです。その結果、内定者は不安を抱えたまま入社しその後のパフォーマンスに影響が出たり、早期離職のリスクを高めたりする原因となっています。
選考プロセスでは、「内定を出す段階までいけば安心」ということはありません。むしろ、この段階で内定を辞退された場合、採用試験をやり直さなければならないリスクもありタイムロスが非常に大きくなります。
入社後
有能な人材を採用した後も、採用担当者の悩みは続きます。またこの段階になると、現場も大きく関わってくるため両者の悩みを合わせて考えていきます。
オンボーディング体制が整っていない:研修担当の不在や業務マニュアル・研修プログラムが確立されていないことから、新入社員はOJTという形で先輩社員から口頭で業務を教えてもらうことが主流となります。結果、入社後のサポートが手薄になり早期離職のリスクを高めたり、早期にパフォーマンスが発揮できなかったりします。
カルチャーフィットの見極め不足:スキル重視で採用した結果、価値観や働き方が合わずにせっかく採用した人材が定着しないということもあります。採用にかかった時間とコストが無駄になるだけでなく、少数精鋭であるためチームに与えるダメージも大きいといえます。
役割や裁量権が曖昧:スタートアップでは事業や組織が急速に変化する成長フェーズにあるため、担当業務や裁量権が流動的です。そのため、役割が不明瞭で採用した人材を持て余してしまったり、新入社員であってもはじめから過大な業務を担わせざるを得なくなるケースもあります。
評価制度やフィードバックの仕組みが整っていない:組織体制が絶えず変化しているため、評価基準やフィードバックの仕組みが固定されていないことが多くあります。結果、社員に評価の透明性と公平性に疑問を抱かれることになり、「成果が正しく評価さない」とモチベーションの低下や離職につながります。
採用は、「入ってもらえれば終わり」ではありません。その人が定着してはじめて、企業は利益を上げられます。そのため、その人が離職しないようにするためのさまざまな方法を考えていかなければなりません。
スタートアップの採用を成功させる7つの戦略
このような厳しい競争下、スタートアップが採用を成功させるためには何をポイントにすれば良いのでしょうか。
ここからは、エイペックスが考える「スタートアップが採用活動を成功させるための7つの戦略」について、詳しくご紹介しましょう。
自社にマッチする「採用ペルソナ」を設計する
求職者に伝えたいメッセージを設計する
スカウトなど「攻め」の採用活動を行う
自社HPやSNS等で採用ブランディングを行う
採用CX(候補者体験)を重視する
カジュアル面談を実施する
転職エージェントの活用を視野に入れる
① 自社にマッチする「採用ペルソナ」を設計する
まずは、募集段階で「条件に合った応募者が来ない」というミスマッチを防ぐため、求める人材の「採用ペルソナ」をしっかりと定めましょう。
採用ペルソナとは、「理想の応募者」を具体的に定義した架空の人物像のことで、「品質業務経験3年以上」のような応募要件とは異なります。「採用ペルソナ」はそこからさらに踏み込み、その人物の志望動機や仕事に対する価値観、性格などもある程度想定して定義します。
採用ペルソナの設計で生まれるメリット:
「どんな人を採用したいか」の認識を会社全体でそろえられる
求人票やスカウト文面の訴求ポイントが明確になる
求める人物像がはっきりしているので、採用活動の効率化につながる
ミスマッチによる早期離職を防げる
面接の評価基準や質問設計にも活用できる
採用ペルソナは、求人票・スカウト文面を考える前の段階で作成しておくようにしましょう。
採用ペルソナの作成で考えたい項目例(すべてを考える必要はありません):
《一般的な情報》
年齢と性別:年齢は、「30代」などではなく「28歳」などのような明確な数字
家族構成:既婚・未婚、子どもの有無、独身者の場合は家族構成
学歴と所属していた部活:大卒か高卒か専門学校卒業かだけではなく、「●●大学の●●部」まで書き出す
職業と収入:例えば「中規模の内資系医療機器会社の営業職、年収550万円」など
《性格や行動特性》
普段利用する情報源:普段、情報収集にどんなWebサイトやSNSを利用しているか
興味のあるコンテンツ:どんな記事やコンテンツに興味を惹かれるのか、よく検索するキーワードなど
趣味:どのような趣味を持っているか、休日はどのように過ごしているか、趣味嗜好(好きな本など)
長所:「面接のときに本人が答えるであろう長所」ではなく、その人物が「日常の場面や過去のなかで、褒められてきたこと」をテーマとする
性格 / 行動特性:どんな人物で、どんな環境で力を発揮できるタイプか(例:「イベント等で率先して皆をリードできるタイプ」「計画性があり、ミスがないか確認を怠らない慎重派」など)
《仕事に関すること》
現在の業務:簡単なキャリアと現在担当している業務や役割(例:「新卒で現在の医療機器会社に営業として入社。循環器領域を中心に首都圏の病院を担当、入社6年目。昨年から基幹病院も担当となったため残業が多くなった」など)
現職への不満や仕事の課題:現職で何に不安を抱いているのか、なぜ退職を考えているのか(例:「決まったルート営業が中心で、自身の創意工夫が活かせない環境に閉塞感を抱いている」など)
転職で得たいもの:キャリアで何を成し遂げたいのか、望んでいるキャリアパス(例:「新しい領域に携わりたい」「キャリアアップしたい」「社会貢献性の高い事業に携わりたい」など)。このときは、「自社がどのような機会を提示できるか」の視点にならないように注意
仕事に対する価値観:仕事をするうえで大切にしていること(例:「年収」「安定」「ブランド力」「プライベートの時間」「成長機会」など)
求める組織文化:求める企業カルチャーやチームの雰囲気(例:「個人の裁量が大きい」「組織の調和や良好な人間関係が最重要のカルチャー」など)
具体的なキャリアビジョン:5年後、10年後にどうなっていたいのか(例:「3年以内には営業所長に昇進、10年以内にはエリアマネージャーに就くことを目指している」など)
ちなみに採用ペルソナは、「どのような人物を採用するのが望ましいか」を社内で共有するためだけに行うものであり、実際の採用で「年齢」「性別」などで応募者を不採用にすることはできません。また、企業の理想を当てはめただけの「外向きの」視座にならないようにすることも、採用ペルソナの活用のポイントです。
実際に、この採用ペルソナとすべて合致している、あるいはマッチング率が非常に高い人が応募してくる可能性は極めて低いと考えましょう。
そのため、実際には採用ペルソナを設定したうえで、重要視する項目の書き出しを行わなければなりません。
採用ペルソナ作成までのステップ:
採用目的を明確にする
経営層や現場にヒアリングして、求める人物像を整理する
架空の人物としてペルソナを設計する
社内で共有して、求人や面接に活かす
採用ペルソナの設定には時間がかかりますが、ミスマッチな人材を採用してしまった場合に比べれば、結果的には時間とコストの節約につながります。
② 求職者に伝えたいメッセージを設計する
スタートアップが求人広告を考えるときには、「伝えたいメッセージ」が特に重要となります。大企業に比べて安定さと知名度に劣るスタートアップにとっては、その事業内容と理念、成長性こそが、ライバルに打ち勝つ要素になるからです。
求職者に伝えたいメッセージは、
理念と理想
自社サービスの強みと優位性
キャリア成長の可能性
ほか、特色のある待遇
の4つの柱で構成します。それぞれ見ていきましょう。
理念と理想
スタートアップにとって、「理念と理想」は応募者に対するもっとも強いアピール材料となります。例えば、新しいコミュニケーションツールを開発する企業であれば、「既存のコミュニケーション方法を見直すことで、言語・人種・業種・障がい・認知能力などに関わらず誰もが快適にコミュニケーションが取れるようにすることを目標としている」などのような書き方ができます。
スタートアップに応募する人の多くは、その企業の理念と理想に共感しています。見方を変えれば、「ビジョンに共感してくれる人、製品の社会的意義を理解してくれる人を採用できるような伝え方」が求められるということです。自社サービスの強みと優位性
レッドオーシャンに新しいサービス・製品を持って乗り込んでいくスタートアップも、ブルーオーシャンに漕ぎ出そうとする企業も、どちらの場合も自社のサービスの強みと優位性をアピールする必要があります。
もっとも分かりやすいアピール事例としては、「高品質・低価格」でしょう。それがなぜ実現できるか、どのような根拠があってそのようにいえるのか、どのような実績を挙げたのかなどを、分かりやすく簡潔にまとめて求人情報として載せるようにしますキャリア成長の可能性
大企業にないスタートアップの大きな強みは、成功すればキャリアアップや年収アップの速度が非常に速いということです。
例えば、「入社1年目から事業のコアメンバーとして活躍し、早期にマネジメントポストを目指せる」「年功序列は一切ない。個人のパフォーマンスと事業への貢献度を正当に評価し、昇給・昇格にダイレクトに反映する」などがアピールとなります。あわせて、ストックオプションの支給について言及しても良いでしょう。ほか、特色のある待遇
大企業に比べて待遇の面で弱いとされるスタートアップですが、だからこそ、他社よりも優位に立てる特色のある待遇を打ち出せれば有利になります。
例えば、「男性の育休の取得期間は平均5か月、入社直後から取得でき、準備金として前払いで70万円まで出す。法律婚ではない場合も対応できる」など、実際に取得の実績があれば紹介しても良いでしょう。
また、スタートアップはハードワークというイメージがあるため、フルリモートやフレックス制度、独自の休暇制度など、働き方の柔軟性を積極的に打ち出していくべきです。場合によっては、これこそが就職・転職を決める決定打となることすらあります。
なお、これらのメッセージは自社の求人(採用)ページ、求人広告、スカウトメール、面接試験など、多くの場面で用いることになります。それぞれの場面でぶれや矛盾がないように、しっかりと関係者間で検討しておきましょう。
③ スカウトなど「攻め」の採用活動を行う
知名度の低いスタートアップの場合、「ただ応募を待つだけ」では大企業に採用活動で勝つことはできません。
そのため、採用においても「営業」「能動的な姿勢」が強く求められます。企業側から優秀な人材に対してスカウトを行う「ダイレクトソーシング」と呼ばれる働きかけを行い、自社の求めるスキル・経験・資格を持っている人に対し積極的にアプローチしましょう。
ダイレクトソーシングのもっともメジャーな手法として、ビジネスSNSであるLinkedInやWantedly、YOUTRUST、もしくは適切な求人サイトを活用して「スカウトメールを送る」方法があります。上手くいけば「スカウトメールが来たから、話だけでも聞いてみようと思った」「スカウトメールから企業の名前を知り、その理念に共感して転職した」という人も出てくるかもしれません。
なお、忙しいなかでかつ多くの人にスカウトメールを送ることになるため、採用担当者はついコピペで同じ文面を送ってしまいたくなりますが、それでは候補者に響く内容にはなりません。
ベースとなる文章はテンプレートでも構いませんが、作成時には、
その人の所持資格や経験、経歴などをよく読む
それを文章に織り込み、なぜその人が募集ポジションに合っているかを伝える
「共感いただけると思った」などの表現を添える
を意識して作ります。また、名前はその人の登録情報からコピペして貼り付け、間違いのないようにします。そして、メールに返信があった場合はすぐに返すのが原則です。
④ 自社HPやSNS等で採用ブランディングを行う
自社を知ってもらうことや、自社のイメージアップのためにはブランディングが欠かせません。自社のホームページやSNSなどを使って、積極的に企業の魅力や特徴をアピールしましょう。社内風景や先輩社員へのインタビュー、キャリアステップを図式などで示すことも有効です。また、必要に応じて外部の専門家(ライターやカメラマン、コンサルタントなど)に依頼すると、より良いコンテンツが作成できます。
なお、「悪名は無名に勝る」といわれますが、採用ブランディングにおいてはこれは悪手中の悪手です。SNSやnoteなどでは慎重な発言を心掛け、同業他社や特定の属性に対する「下げ」は厳禁とします。可能であれば複数人で運用・構築に関わるようにしましょう。
⑤ 採用CX(候補者体験)を重視する
採用CX(Candidate Experience)とは、「応募してきた人が体験する一連の選考プロセス」を指し、近年どの企業も重視している施策です。
大切なことは、候補者の最終的な合否にかかわらず、選考を通して自社に良い印象を持ってもらうことです。採用の際に、内定承諾率や入社後のエンゲージメントが向上したり採用のミスマッチを減らせたりするほか、不採用になった人にも「ここの企業の対応が良かったから、他の人にも伝えよう」というプラスの印象を持ってもらえます。
採用CXの向上のためには、
丁寧な説明
迅速な返信
透明性の高い評価基準
フィードバックの提供
関係者間でぶれのない情報提供
などが有効です。
⑥ カジュアル面談を実施する
認知度が低いスタートアップでは、転職希望者に自社の魅力を伝え志望動機を高めてもらうために、カジュアル面談を実施している企業が多くあります。
多くの求職者は、カジュアル面談なら「まだ応募ではない」という心理的なハードルが低く、気軽に話を聞きに来やすいのと、企業側もカジュアル面談で候補者の本音や潜在的な可能性を探ることができます。そのほかにも、早期にお互いのミスマッチを防げたり、双方が合意すればすぐに次の選考ステップに進むこともでき、お互いの負担を減らせるというメリットもあります。
カジュアル面談は、「応募者がこの企業に応募するかどうかを決めるため」にあるものですが、事前に履歴書・職務経歴書を提出してもらうことで、その人のポテンシャルを測れたり的を得た質問をすることができます。
⑦ 転職エージェントの活用を視野に入れる
短期間で即戦力人材を集めるのが命題である場合、採用の専門家である転職エージェントに任せるのもひとつの手です。
特に、リソース不足で採用のノウハウがまだ蓄積されていない場合、採用代行サービス(RPO)を活用するのがおすすめです。上記の採用ペルソナの設計や求人票の作成から一括して採用活動を委託することができ、担当者は事業拡大を目指すための本来の業務に注力することができます。
仮に自社でスカウトを行っても、CxO候補や部門長などの人材は転職のモチベーションが低く、また一般の転職サイトに登録していないことが多いためリーチが非常に困難です。
転職エージェントは独自の候補者ネットワークを持っており、エイペックスのようなハイクラス人材・専門職人材を専門としている転職エージェントにスカウトを任せることで、大幅な労力の削減が可能です。プロに任せてミスマッチのリスクを減らすことで、結果的にコスト削減につながることが期待できるでしょう。
スタートアップが求める人材像と採用基準

スタートアップにとって、採用にかかるコストは非常に大きいものです。そのため、事前に「どのような人材が必要か」について考え抜き、計画的に選考を進めることが必須です。
そこで、スタートアップにとって特に重要となる人物像と採用基準についてご紹介しましょう。
会社のミッションや価値観に共感しているか
「自社の持つ理想や価値観、果たすべきミッションに共感しているかどうか」は、スタートアップの採用において最も重要な項目です。スタートアップは少数精鋭であるため、ひとりでも共感していない人がいると企業全体に直接的な悪影響が出るからです。
反対に、会社の理想やミッションを自分ごとのようにとらえてくれる人であれば、事業がまだ軌道に乗っていないときでも「自分の夢でもあるこのプロジェクトのためにがんばれる」としてモチベーションが維持しやすかったり、社員の士気を高め組織の求心力となってくれたりします。
採用面接では、候補者が表面的な部分ではなく、経験や具体的なエピソードに基づいて理念や価値観に共感しているのか確かめるようにしましょう。
主体性があり自ら意思決定ができるか
スタートアップでは社員一人ひとりの采配権が大きく、主体的な行動が求められるシーンが非常に多いといえます。
そのため、
自分で課題を見つけられる
自分で勇気をもって意思決定ができる
「人に聞く」ということを、必要な場面で過不足なく行える
失敗を恐れない、失敗を共有できる
を満たした人材を採用する必要があります。
ここで大切なのは、「迅速な意思決定ができる人はいても、常に正しい答えを出せる人はいない」ということを企業側もよく認識しておくということです。
「主体性を持って決断できるが、必要に応じて自ら人に意見を求め、失敗を隠さない人」こそが、本当の意味で主体性を持った人間であるといえます。
これを知るためには、「あなたが自ら下した判断での失敗経験を教えてください」などと質問し、自主性と傾聴能力、失敗からのリカバリー手法を聞くと良いでしょう。
なおこの質問では「失敗経験を教えてください」とし、直接的には「どのようにリカバリーしたか」は聞きません。本当の意味で主体性のある人は、質問者の意図を正しく理解し、リカバリーの手法までを回答に組み込んできます。
マルチタスクに対応できる柔軟性があるか
一部の専門職を除き、基本的にスタートアップでは一人ひとりの社員に対しマルチタスクを求めることになります。
そのため、複数の業務を幅広く柔軟にこなしていける人材を採用する必要があります。またその人材が、組織全体の効率化などを提案できるようならばなお望ましいでしょう。
柔軟性を確かめる質問としては、「予期せぬトラブルが発生したときに、実際に行った対応策を教えてください」などが良いでしょう。
マルチタスクについて聞くときは、シンプルに「マルチタスクを行った経験を話してください」でも構いませんが、「在職中に資格を取得しておられますが(※『介護』『子育て』なども可)、どのように両立していましたか」などのように聞くのも効果的です。
学習意欲と成長志向が高いか
スタートアップは事業も組織も日々変わり続けるのが特徴です。そのため、常に学び続ける姿勢と会社とともに自己成長していく姿勢がないと向いていません。自ら成長しようとする人は、周囲にも刺激を与え組織の成長を加速させることができます。特に、「不確実な環境でもリスクを恐れず、新しいことにどんどん挑戦できる姿勢がある」人がより向いているでしょう。
採用面接では、「いま習得したいスキル(資格)を教えてください」などと質問すると良いでしょう。向学心が高い人は、常に「新しいスキル(資格)の取得」を目指していることが多いため、この質問に対してしっかりと答えられるはずです。
スタートアップの採用でよくある失敗
スタートアップの採用でありがちな失敗として、下記の4つが挙げられます。これらをあらかじめ克服できるようにしておきましょう。
リスクを告げず、ポジティブな情報しか伝えない
「有能な人材を取りたいがために、自社の魅力しか伝えない」「考えられるリスクを伝えず、採用を進めてしまう」ことは、スタートアップがよく行ってしまいがちな間違いです。
これは意図してリスクを隠すケースだけではなく、
人材紹介会社に任せきり
汎用的な求人広告・求人文句だけを使用している
現場の意見を上手く聞き取れていない
などの状況でも起こりうることです。
採用段階では、「あなたに期待している役割」「目指してもらいたい目標」とともに、「現状の課題」「福利厚生」「評価制度」などについても誠実に伝えましょう。また、マイナスにとらえられがちなこと(実際にハードワークとなるポジションで、質疑応答のときに「残業はありますか?」と聞かれるなど)も、ごまかさずに誠実に答えることが必要です。
リファラルに頼りすぎる
リファラル採用は、採用に関する時間的・物理的コストを大きく削減する手助けとなります。しかしこれだけを重視すると、
専門性が偏る
多様性が損なわれる
人間関係のしがらみが生じ、公正な判断がしにくくなる
といったデメリットが生じます。そのため、紹介比率には上限を設けることが望ましく、さまざまな採用手法を組み合わせて意図的にバランスを取ることが必要です。
採用条件や評価基準が曖昧なまま採用する
採用条件や評価基準が曖昧なまま採用活動を進めてしまうと、大きなトラブルにつながりかねません。
特に、
残業の有無
年収の計算方法
時間外労働分の給料の計算方法
昇進などの評価指標
休日・有給の日数
勤務地・転勤の有無
は最重要項目なので、しっかり整理しておきます。
また、これらは応募者から聞かれやすい項目でもあります。聞かれた場合は誠実に答え、事実ベースで話をするようにしましょう。なお即答できない場合は、「折り返し回答します」として持ち帰り、後日丁寧に回答するようにします。
「労働条件が違った」という事態になれば、採用した人物のモチベーションが大きく下がるだけでなく、裁判などに持ち込まれて敗訴になる可能性すらあります。
即戦力人材のみを求め続ける
スタートアップが即戦力人材を求めるのは、ごく当然のことです。
しかし、そればかりでは学習文化が根付かず、組織の硬直化を招き変化への対応力も弱まります。オンボーディング後の育成計画やメンター制度などを整備し、潜在力の高い人材の成長を支援していく体制も整えるべきです
また、即戦力を求める場合でも、「営業やプレゼンもできて、新しい発想もあり、その試作品を作り上げることができて、英語もできて……」などのように、「複数の分野において、専門家以上(あるいは専門家と同等の)能力を持つ人」を求めることは控えるべきです。
スタートアップに適した採用手法まとめ
人材を確保するための採用手法は、数多くあります。ここでは、特にスタートアップ企業向きのものを取り上げて、それぞれの特徴とメリット・デメリットについて解説していきます。
リファラル採用:社員や関係者からの紹介で人材を採用する方法。「紹介キャンペーン」などを開催して、紹介を促しても良い。カルチャーフィットしやすく、定着率も高めでコストもほとんどかからないのがメリット。ただし、これだけに頼ると専門性や多様性が偏り、人間関係のしがらみが生まれやすい
ダイレクトソーシング(ダイレクトリクルーティング):求人媒体やSNSを通じて、企業が直接候補者にアプローチする方法。ターゲッティングしやすくスピードと精度が高いのが特徴。ただし、相手のプロフィールを読み込む熱意と時間がないと上手くいきにくい
オウンドメディアの活用:自社サイトやSNS、ブログなどを通じ企業の文化や働き方を発信し、共感を呼ぶことで応募につなげる手法。ただし、本格的な立ち上げと直接的な応募につなげるまでに時間がかかる
求人媒体への投稿:求人情報を求人サイトに掲載し、広く求職者にアプローチする手法。ただし、コストがかかるのと多数の競合他社も掲載しているため、求人票の内容に工夫が必要。ポジションにマッチしていない応募者も多く、確認や返答に時間がかかる
転職フェアなどのイベント出展:一度に多くの候補者にリーチでき、その場で選考や面談が可能であること、企業の魅力を直接アピールするPRの場にもなるのがメリット。ただし、人的リソースと準備工数、出展費用がネックとなる
インターン・業務委託採用:実務を通じて相性を見極める方法。採用前にリアルな働き方を体験でき、採用側も人物像を把握しておりミスマッチが少ない。実際に業務を通じて相手を見極めていくため、時間面やコスト面の負担がやや大きい
転職エージェント:成功報酬型(採用が決定してはじめて費用が発生する)が一般的で、初期費用がなく相談も無料。採用したいポジションによっては、「リテイン(専属型)サーチ」(採用活動の全プロセスを委託できる)やRPOが最適な場合もある。担当者との相性によって進めやすい・進めにくいはあるが、担当者の変更を願い出ることは可能
スタートアップ採用面接アドバイス:エイペックスのコンサルタントが語る【動画あり】
スタートアップが採用面接を行う際には、「候補者がどのような価値観や働き方を求めているのか」「スタートアップにフィットする人物像とはどのような人材か」を正しく理解しておくことが重要です。
下記のポッドキャストでは、ITチームのマネージャーを務める幾島 俊が、日本のスタートアップ市場の現状や報酬制度、スタートアップを選ぶ人材の特徴などについて、具体的な事例を交えながら解説しています
スタートアップの採用戦略を検討する上での参考資料として、ぜひご活用ください。なお、ポッドキャストの全編はYouTubeにてご視聴いただけます。
エイペックスでのスタートアップの採用成功事例
スタートアップ企業のなかには、エイペックスのサービスを活用することで採用において大きな成功を収めた企業も多く存在します。下記の成功事例を見ていきましょう。
成長中スタートアップがクラウド/セキュリティのエキスパートをデリバリーマネージャーとして採用
転職者プロファイル
クラウドインフラやセキュリティ分野で、15年以上の経験を持つテクノロジーコンサルタントです。
前職の大手外資系IT企業では、ポストセールス領域を中心にシステム設計・クラウド移行・セキュリティソリューションの導入支援など、エンタープライズから通信・公共分野まで幅広い顧客を担当されていました。
その後、「より広範な責任と裁量権で、自ら手を動かして成長フェーズの企業を支えたい」と考え、ITインフラやセキュリティを強みとする成長中テクノロジー企業をターゲットに転職活動を開始。結果、エイペックスでの初回面談からわずか約3週間で現職のオファーを獲得しています。
現在は、IoTデータの安全な流通を支えるソフトウェアを開発する日本発ディープテックスタートアップでデリバリーマネージャーとして活躍しており、エンタープライズ顧客向けのプロジェクトにおいてサービス提供や技術支援を統括し、カスタマーサクセス体制の強化に取り組んでいます。
コンサルタントが考える採用成功のポイント
この採用成功事例のポイントは、なぜこの候補者が「現職を離れてまで転職したいのか」の核となる部分に採用企業が終始フォーカスできたことです。大手外資系IT企業に勤め、また成長領域での豊富な経験を持つこの候補者の経歴は、当然多くの企業から魅力的に映ります。もともとの転職の動機があっても、多くの企業からのアプローチや条件交渉のなかで、目先の好条件に引っ張られ転職の軸にぶれが生じてしまうのは、ある意味当然のことです。
今回のケースでは、毎回の面接後に簡単でも面談を行うことで、企業からのフィードバックとともに転職のテーマについて再度すり合わせができたことが成功のポイントでした。「転職で何を実現したいのか」について冷静に再確認していけたことで、結果的に転職を通じた自己実現につながったと感じています。
転職活動は日常的なイベントではないため、特に面接後は候補者は近視眼的な傾向になりがちです。コンサルタントが常に間に入ることで候補者は客観的な見方を保つことができます。また、企業側にもエージェントが候補者の本質的な希望を伝え続けることで、企業が選考プロセスを通じて終始一貫したアピールを保つことができ、結果候補者が「この会社なら」と感じることができたのだと思います。
スタートアップの採用で大切なこと
スタートアップの採用では、時間的・コスト的・人的なリソースが限られるため、求人媒体の利用数やスカウトメールの作成などに制限が出てきます。そのため、一つひとつの取り組みの精度を上げることが採用成功の鍵となります。
そのためには、
スタートアップならではの新規性や成長性を打ち出す
既存の企業にはない福利厚生や新しい試みなどを全面に出す
社員全員が採用を自分ごととしてとらえ、全方向からアプローチする
今すぐの採用だけでなく、継続的な人材確保のためのアプローチを行う
などの方法を取りましょう。
また、スタートアップの採用では、経営陣や管理職、スペシャリストなど希少人材の獲得が求められる場面も少なくありません。こうしたポジションは、候補者の母数が限られているうえ、情報の秘匿性や条件交渉の難易度も高く、通常の採用手法ではアプローチしづらいのが実情です。
このようなケースでは一般の転職エージェントではなく、エイペックスのように業界に精通したエグゼクティブサーチの力を借りることで、採用成功の確率を大幅に上げることができます。エイペックスが持つ独自の候補者ネットワークを活用しながら、専任のコンサルタントが募集要件の整理、候補者のサーチ・スカウト、条件交渉、入社後のフォローまで一気通貫で支援を提供するため、採用の質・スピード・安定性が格段に向上するからです。
特に、採用競争が激化する現在では、限られたリソースで最大の成果を出すために、エイペックスのような専門型の転職エージェントとの連携は不可欠です。自社だけで抱え込まず、信頼できるパートナーと協業することで、貴重な時間と労力を事業成長に集中させましょう。
採用にお悩みの担当者の方、情報収集のため話を聞きたい方は、下記のボタンからぜひお気軽にお問い合わせください。



.png)


